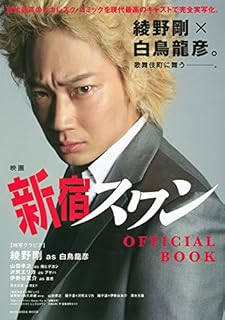映画の本となると話はどこからでもはじまる講演会「映画批評をめぐる冒険」第三回まとめ(講師:佐野亨、モルモット吉田、岡田秀則)
2015/11/26
Contents
・それぞれの映画本とのかかわり
モルモット吉田:
映画の外側含めた書き方をする人に植草甚一さんや現代では中原昌也さんとかもいて、そういうのは書いてみたいけど絶対に真似のできない芸。
佐野亨:
話が変わるんですけど、同年代に「川本三郎が好き」と言った時に「古い映画が好きな人ですよね」と言われてショックだった。初期著作は是非とも若い人に読んでほしい。岡田さんは仕事とのかかわりにおいてどういう映画本を読んできました?
岡田秀則:
大学院に行かず就職して、それからフィルムセンターに入ったので本格的な映画史研究を何も読んでないことに気づいて、田中純一郎も読んでない申し訳なさに「批評」ではなくて映画史の方向に入っていった。仕事も仕事なので現在は資料的に映画本を読まざるを得ないことも多い。
モルモット吉田:
自分は例えば黒沢清の『リアル』と『ネッシー』という映画を絡めて4000字で書いてと言われたときに、あらすじ含めて既存資料で書くこともできるんですが、文章がうまけりゃという感じで資料を集める方向にいく。映画になってないネッシーという幻の映画の情報はそもそもどこにあるのか、と台本を探してくる、ヤフオクで調べたり、古書店を周ったり、『ネッシー』の台本に関しては早稲田の演劇博物館で苦労してみつけた。
・未発表シナリオや貴重資料の収集について
(注:ここから先は内容が濃かったのでしっかりと追えなかったですwすいません箇条書きです)
・『別冊映画秘宝』で連載している高鳥都「映画と愛国」の凄さ(佐野)
・切通理作『山田洋次の<世界>』は一次資料をもとに書かれた。
・映画にならなかったシナリオを矢口書店で収集。黒沢
→「サトウハジメ回想録」「私の東映30年」「娯楽映画の骨法」「いとうあきおシナリオ選集」といった貴重資料の紹介。
・映画本収集家の高齢化のなかでモルモット吉田は期待株(岡田)
・2010年前後から地元の映画人の記念館や発掘の度合いが進んでいる。しかし現場の意識は高いが、お金がついてこない現状もある。そのなかでも市川市の「水木洋子邸」は凄い。実際に行って資料を「使える」というのが重要。(岡田)
・映画の作り手の本、そして伊丹十三について
・『鈴木清順エッセイ・コレクション (ちくま文庫)』は面白い。
(↓系譜的な映画の作り手の本)
- 『和田誠新人監督日記』
- トリュフォー『ある映画の物語』
- 伊丹十三『「マルサの女」日記』
- 大根仁『モテ記~映画『モテキ』監督日記~』
佐野亨:
伊丹十三はこだわるべき。これだけ才能ビシバシと多方面に出して、以前はテレビでも劇場でも作品は流れてたのに冷遇されている。蓮實重彦門下の影響もあるのかもしれないけど活動全体を見るべきで。ある意味、少し前までの角川映画に近い扱い。
・佐野亨が選ぶ映画の本50冊をネタに
(こちらから読むことが出来ます。PDFファイルです)
ここから話に出た映画本
海野弘『エデンという名の映画館』・・・映画のポスターやインテリアについて。
大場正明『サバービアの憂鬱』・・・アメリカの郊外をテーマにした映画論。傑作。
山根貞男『映画狩り』・・・一番やくざっぽい時期。顔写真がコワい。
松本俊夫『映像の発見―アヴァンギャルドとドキュメンタリー』・・・明晰
土本典昭『映画は生きものの仕事である―私論・ドキュメンタリー映画』・・・観察への距離感と自己について、非常に読みごたえがあり。もっと読まれる必要がある。
草森伸一『悪のりドンファン』・・・コマーシャルをめぐる雑文。
岡田秀則:
自分が関わっている「シネマブックのひそかな楽しみ」(注:8月2日まで東京国立近代美術館フィルムセンターで行われている展覧会)は映画本のデザインの凄さがわかる。
モルモット吉田:
デザインの凄い映画本といえば金井美恵子さんの『映画、柔らかい肌』
・最近の映画本と昔の映画本
モルモット吉田:
『大島渚1960』。監督の作品全体ではなく1960年代の3本を取り上げて企画や方法論の検討をしている。
佐野亨:
昔の本は注釈が凄くて。『ゼロ年代アメリカ映画100』はまだそこまで注釈を入れてないけど元ネタの『70年代アメリカン・シネマ103』は紙面に白い部分がないぐらいの注釈、ほかの年代シリーズも最初の本以降は注釈がどんどんふえていった。
岡田秀則:
フィルムアート社の本も『ヒッチコックを読む―やっぱりサスペンスの神様!』などの一連のシリーズは注釈がめちゃくちゃ多かった。
・会場からの質問
Q1、購読されている映画雑誌は?
共通で『キネマ旬報』『映画秘宝』『映画芸術』『nobody』『シナリオ』
モルモット吉田:あとは『Cut』とか『BRUTUS』の映画特集、最近では小津安二郎の特集が良かった。
Q2、さっき話した「ホイチョイプロダクション」についてもう少し詳しく
佐野亨:「ホイチョイ・プロダクション」の系譜というのは、もう少し映画史の流れに位置付けるべきで、そういうのはけっこうある。たとえば『釣りバカ日誌』をちゃんと馬鹿にしないで1から見たりして作風や流れをまとめたり、「ホイチョイプロダクション」もそうした意味で重要な要素を含んでいると思う。
岡田秀則:角川映画もようやく中川右介さんの『角川映画 1976‐1986 日本を変えた10年』という本で色々なことが明らかになった。そういう分野はある。たとえば松竹系とかの流れもまだまだ発掘の必要がある。
告知としてモルモット吉田さんのお仕事『新宿スワンオフィシャルガイドブック』
岡田秀則さんの携わっている企画として東京国立近代美術館フィルムセンター展示室で開催中の「シネマブックのひそかな楽しみ」(会期:2015年4月14日(火)-8月2日(日))
ということで三回目は今までで一番映画本についてのコアな話が続きました。文脈を全く知らないので流れが前二回以上にぶつぶつと切れてしまい申し訳ないです。
本文中にもリンク先を書きましたが、
「佐野亨・選僕が20代までに読んで滋養になった50冊の本」は凄い役に立ちます。
この中で2015年現在、値段が高くなってしまっているのが↓
- 村上春樹、川本三郎『映画をめぐる冒険』(講談社)
- 渡辺武信『ヒーローの夢と死 映画的快楽の行方』(思潮社)
- 滝本誠『映画の乳首、絵画の腓』(ダゲレオ出版)
- 大場正明『サバービアの憂鬱 アメリカン・ファミリーの光と影』(東京書籍)
- 芝山幹郎『映画は待ってくれる』(中央公論社)
- サミュエル・フラー『映画は戦場だ!』(筑摩書房)
- ルイス・ブニュエル『映画、わが自由の幻想』(早川書房)
といった感じです。
さてこれで「映画批評をめぐる冒険」全三回終わりました、映画批評もそうですが、淀川長治の凄さを文脈込みで教えてもらったり、映画本の奥深さと魅力を知り実際に読むきっかけとなった大変素晴らしいトークショーでした。
講演会をどこまでまとめていいのか、そういうことにも注意を払うようになったのも学びになりました。
「石毛家二階ギャラリー」は他にも様々なイベントを行っているので、是非このまとめで気になった方はちょくちょく覗いてみてください!(公式サイトはこちら)
残りは「番外編」ですが「映画放談」ということで、あんまり書けることが少なそう。
【関連記事】
関連記事
-

-
良作・奇作・怪作・傑作の映画祭「未体験ゾーンの映画たち 2015」がやっぱり凄い
ヒューマントラストシネマ渋谷で毎回好評の映画祭「未体験ゾーンの映画たち」が20 …
-
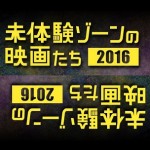
-
新春映画祭「未体験ゾーンの映画たち」より気になる作品を10本紹介
さて今年もこの季節がやってきました。 さまざまな理由によって映画館で上映すること …
-
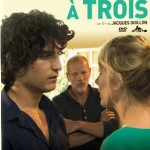
-
ジャック・ドワイヨン『三人の結婚』感想、新文芸坐シネマテーク備忘録
体調とお金の都合でしばらく休養していた「新文芸坐シネマテーク」へ久しぶりに参加。 …
-

-
【お知らせ】早稲田祭1日目にチベット映画『オールド・ドッグ』の上映会&講演会を開催
「早稲田祭2014」の1日目、11月1日の午後14時からチベット映画『オールド・ …
-
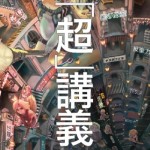
-
『 じぶんの学びの見つけ方』刊行記念、高山宏×石岡良治トークショーまとめ
2014年10月3日(金)久しぶりに神保町。目的は東京堂書店で行われる高山宏と石 …
-
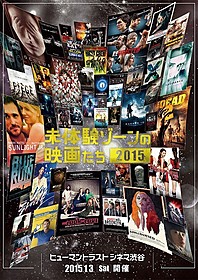
-
ネイキッドロフトで行われた「未体験ゾーンの映画たち2015予告編大会」まとめ
2015年1月からヒューマントラストシネマ渋谷で行われている映画祭 「未体験ゾー …
-
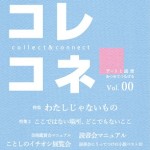
-
文化をあつめてつなげる新雑誌『コレコネ』創刊のお知らせ。
自分が所属しているサークル「Arts&Books」でこのたび新しく雑誌を …
-
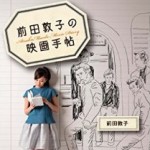
-
「まだまだ映画を見続けます」『前田敦子の映画手帖』刊行記念トークショー(暫定まとめ)
朝日新聞出版刊行『前田敦子の映画手帖』の刊行記念トークショーに当選したので、6月 …
-
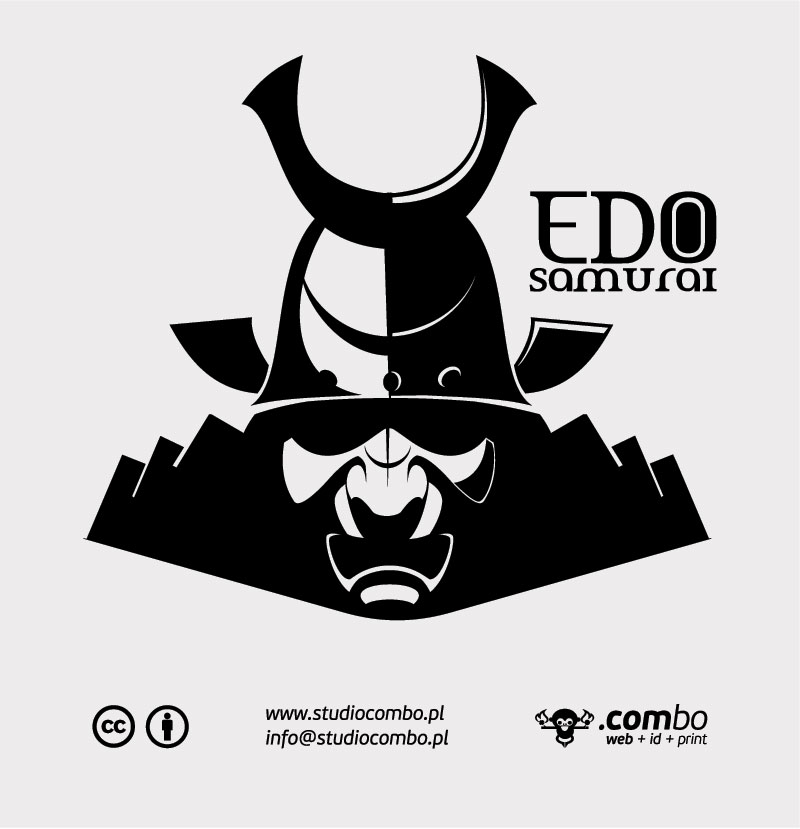
-
新文芸坐・春日太一の時代劇講座(10月20日ver)
「春日太一と新文芸坐のオススメ時代劇講座」と称し10月18日(土)から貴重な時代 …
-

-
春日太一の時代劇講座(10月23日ver)
先日こちらの記事のなかで(会場内にビデオカメラがありましたのでたぶん書籍化するか …