【書評】おそるべきめいちょ『ニュースをネットで読むと「バカ」になる ソーシャルメディア時代のジャーナリズム論』(上杉 隆著、KKベストセラーズ刊)
2015/11/27
様々な歴史的な経緯を経て、ネットには大手メディアが報じない真実があるというのは嘘であると言う著者の言葉は、氏の著作(たとえば『なぜツイッターでつぶやくと日本が変わるのか』など)でネットの未来を語っていたがゆえに苦渋の言葉だろう。その心労は察するに余りある。
著者の苦悩が満ちている本
その苦悩ゆえだろうか。大先輩であり尊敬していた池上彰を自ら調査せずジャーナリストではないと強めの言葉で非難するとき、自身の著作を使用する許可を池上彰が求めた際に署名入りを要求したが返事はなかったということを例にあげているが、氏はそれがどういう著作のどういう文章に関して求められたのかという「エビデンス」を書き忘れている。
エビデンスを書かなければならないという趣旨の本でもエビデンスを書き忘れることもある、読み手にとっては実に強い教訓だ。
ある一つの記事にとってソース、クレジット、コレクション、バイライン(署名)、オプエド(記事内においての反対意見)こそが重要であり、それを踏まえたうえで自らの足で取材し、実際に調べていく誠実な態度こそジャーナリストたりえるという著者の言葉は「ニューヨークタイムズ」で世界基準の取材方法を学んでいるからこそ言えるのだろう。
日本ではコメンテーターが別分野に対しても堂々と発言し、評論家とジャーナリストの区別がなされないまま、ジャーナリストの立場が弱いことや記事に関しても匿名的な状況にあることを氏は「クレジットやソースがないのであれば空想で記事を書くことが出来る」と強く懸念している。
出てくる敵の数々
そういう「誠実」な態度だからか、それにしても非常に敵が多い、著者への圧力も常にかかっているようだ、一読者の私にはそれが見えづらく誰と戦っているのかがよくわからないが、非常に巨大な悪と戦っているらしく、たまに羅列される名前には現在の首相まで出てくる、大変である。
「彼らの悪しき特徴は、ジャーナリストなり論客としてメディアに出ている割には、議論には応じないことである。ツイッターなどでは挑戦的な発言を繰り返しているネットジャーナリストやネット評論家に限って直接の論争を避けるのだ」p131
普通の人が書いたらブーメランのように返ってくる指摘も堂々と書けるのは、本人が自前のニュースサイト「オプエド」などで、現状のメディアの問題について真剣に考えているからだと察せられる。
反対意見をキチンと取り上げる、多様性に満ちた精神はこんな記述からもわかる。
「絶対的に正しいという思い込み自体がリテラシーを身につけるための阻害要因になる」だからこそ「多少耳触りが悪くても、自分とは違う意見を聞く必要があるし、それにいちいち憤慨しないだけの度量を持ち合わせる必要があるだろう」(p198)
まず日本社会における情報リテラシーを強化していくことを辛抱強く続けていかないといけないと思う(p13)と述べているとおり、これからも数多くの敵を増やしながら上杉隆は戦うのだろう。そしてジャーナリズムの原則に基づかない報道や記事あるいは記者を「誠実」に批判していくのだろう。
著者はおそらくこの本すら鵜呑みにするなと言っているに違いない!
そうした信念を社会全体で育てていかないといけない。と本書冒頭で記しているとおり、わかりやすい言葉や美辞麗句で彩られた情報こそ我々は疑っていかねばならない。おそらく、そのように論じる著者の射程はこの本すらも視野に入れている。そうに違いない。『ニュースをネットで読むと「バカ」になる』という本自体が、ここにも様々な間違いがあるんだぞという読者のリテラシーを鍛えるための著者一流の仕掛けなのだ。
最後に自分が一番感動した言葉を引用して記事を終える。
「これは私がいつも言っていることだが、人間は誰だって間違えることがあるのだ。間違いを避ける以上に大切なのは、間違いがわかったら速やかに訂正して、新しい情報を伝えることである」(p132)
【関連記事】
関連記事
-
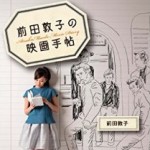
-
【書評】初々しい言葉の連なり『前田敦子の映画手帳』(前田敦子・朝日新聞出版)
映画を見ないとその日は落ち着かないくらい、いま映画にはまっています。一日に何本も …
-
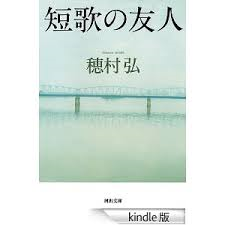
-
穂村弘『短歌の友人』書評~友達作りの方法論~
「俺にもできる」 短歌を作ろうと思ったのは1年ぐらい前に読売新聞を読んでいた時だ …
-
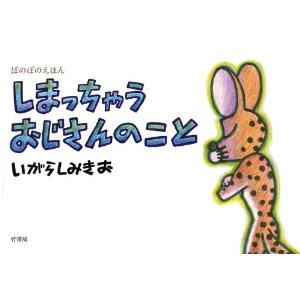
-
知ってる人は知っている名作「ぼのぼの絵本」
「2015年はぼのぼのが熱い」と言う記事を書いてそれなりにアクセスがあるみたい …
-
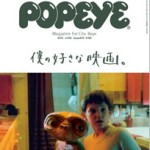
-
雑誌『POPEYE6月号』「僕の好きな映画」特集は時に面白く、たまにむかつく
男「ETってやっぱ面白いよね」 女「わかる。あたしなんてあのテーマ聞いただけでう …
-

-
『怪談短歌入門』書評~怖さには構造がある、短歌篇~
Contents0.0.1 1 陰翳礼讃、隠すことの美学2 定型詩には、隠すこ …
-

-
「最前線を走る創作者たちとのガチ語り」西尾維新『本題』(講談社)書評
西尾維新:自分の中にはそのつど「今」しかなくて、かっちりと『こうい …
-

-
人類を存続させる思いやり『中原昌也の人生相談 悩んでるうちが花なのよ党宣言』(中原昌也、リトル・モア)感想
「中原昌也」の「人生相談」、タイトルの段階でこの本は面白いに決まっているが、最初 …
-

-
寝る前にアントニオ・タブッキ『夢の中の夢』(岩波文庫)を読む
読書日記をつけてみることにしました。まずは一冊目として タブッキ『夢の中の夢』に …
-
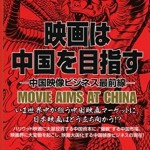
-
【書評】『映画は中国を目指す』(洋泉社・中根研一)
「アイアンマン3」「ダークナイトライジング」「パシフィック・リム」・・・近年のハ …
-
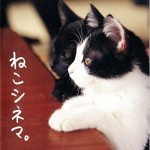
-
『ねこシネマ』を読んでロシア映画『こねこ』を見て悶えて日が暮れて
なにやら猫がブームである。 書店に行けば猫関連の本で棚は埋め尽くされている。自分 …


