「最前線を走る創作者たちとのガチ語り」西尾維新『本題』(講談社)書評
2015/12/02
西尾維新:自分の中にはそのつど「今」しかなくて、かっちりと『こういうものを築き上げよう』という図を描いていないということでもあるのですが、<物語>シリーズもずいぶんたくさん書いてきましたけれども、書くタイミングが一か月違ったらぜんぜん別の小説になっていただろうなとほんとうに思うんです。何を書くにしても、それにふさわしい時期というのがあるんじゃないですかね。
辻村深月:その時期のずれが、一年単位じゃないのがすごいなぁ。一日一日、なんですね。
西尾維新:一日に二万字書くのが、今のスタイルです。
辻村深月:二万字!?
『本題』p178より
『本題』は2002年に『クビキリサイクル 青色サヴァンと戯言遣い』でメフィスト賞を受賞し「京都の二十歳」として小説家デビューした西尾維新初の対談本である。
講談社
売り上げランキング: 46948
顔も出自もよくわからないまま『戯言シリーズ』『刀語シリーズ』『物語シリーズ』等の著作を異常なスピードで刊行しているが、『西尾維新クロニクル』に掲載された細かいインタビューを除きガッツリ自身のことや創作に関してまとまった形で語ったことはなかったので非常に貴重な本だ。
(*書いてて「あれ?」と不安に思って調べたら、むかし東浩紀が発行していたメルマガ「波状言論」で色々と語ってた。でも相当初期の話だから許しておくれ、前篇だけネットで読むことができるがこちらもデビュー当時の話をしていて面白い)
そして、気になる対談相手は・・・
「ラーメンズ」の小林賢太郎、『鋼の錬金術師』が代表作の漫画家・荒川弘、『ハチミツとクローバー』等の漫画で有名な羽海野チカ、直木賞作家・辻村深月、芥川賞作家・堀江敏幸というなんだかとんでもないメンバーとなっている。
「どう言葉を高めているか」、「キャラのセリフには挨拶と感謝のことばをなるべく入れるよう心がけたとはどういうことか」「才能を与えられてしまった者たちの苦悩に関して」「物語作りのモチベーションはどこからくるか」「あるコミュニティなど群生を描く姿勢を教えてほしい」・・・。
西尾維新が今知りたいこれらのテーマを彼・彼女らに手紙で知らせ「本題」というタイトル通り直球で語り合う。脱線したと思えば急に最初と繋がったり、どうでもいい小ネタが挟まれたと思ったら、急に凄い裏話が出てきたり、魅力的な言葉の数々とその構成。これ、まるで西尾維新の小説のようである。
ちょっとどうかと思うぐらい全力で好きです、ファンですと対談相手に言うもんだから時々西尾維新がめちゃくちゃヒートアップしていき、例えば荒川弘との対談ではその溢れんばかりの『鋼の錬金術師』に出てくるグリード様への愛を語る。
この本が面白いのは西尾維新はそういうファンでありながら創作者という立場なので、どう作品やキャラクターを作っているかをファン目線から創作者の目線に繋いで相手に突っ込んだことを聞いてくれることだ。
だから荒川弘からこんな発言を引き出せる。
荒川弘「『鋼の錬金術師』のエドワードとか『銀の匙』で言えば主人公の八軒なんかもそうですけど、「考えすぎだよな」みたいなところです。エドワードの弟のアルフォンスなんかもそうかもしれません、あの兄弟は人のことを考えすぎだから、もっと自分のことを考えればいいのに。そうできなくてガチガチに縛られてる感じはあります。でもそういうやつらだからしゃあないな、こいつらに舵を持たせて物語を進めていこうか、となるわけです」(p104)
そのファン+創作者の目線が一番強く発揮されたのが羽海野チカとの話である。といってもこの場合に限っては西尾維新がそれをやられる側だった。創作に大幅に取り入れてると明言しているぐらい西尾維新の作品を好きな羽海野チカが、普通だったら相手が傷つくかもしれないと考え、途中で会話を止めてしまうあたりを踏み越えていく阿良々木月火のその苛烈な意思への愛を語りまくる。
語り続けること、喋りつづけること、「言って話してこじれても続けなければいけないこともあるのかな」と<物語シリーズ>を読んで考えた羽海野チカに対し、西尾維新は「物語シリーズ」の会話についてこのように言う。
(<物語シリーズ>は)バトル漫画とかバトル小説とかのイメージで、戦いとしての会話をしていたりするので。会話パートではどちらが議論に勝つかは事前にはほとんど決めずに書いています。小説全体の大まかなストーリーラインというのはもちろんある程度は事前にありますけれどもキャラクター同士が議論を始めた後の着地点は、もうそれぞれの立場だったり論争力だったりに依ってしまっていて(p119)
喋ることで戦い、その結果傷ついても、何かの信頼が生まれる。確かに<物語シリーズ>にはそのような描写が非常に多い。「相思相愛」のようにお互いの本を読みこんでいる二人の対談はこのようにとても興味深く、そして笑える。
しかしテーマ「才能」について差し掛かった途端にグッと「怖い」発言が出てくる。
西尾維新、羽海野チカは自分たちを「創作をせざるを得なかったもの」として語る。そして才能とは「他の事が何も出来ない」ということでもあると言う。
ここで有名な一万時間の話が出てくる。なんでも一万時間やってみればその分野で頭角をあらわすというあの話だ。(他の事をあきらめて一万時間その分野に邁進することで開ける道とビジネス分野で肯定的に語られがちであるが、この文脈で言えばそもそも何もできなかったがゆえにその時間を費やさざるを得なかったということかもしれない)
だが羽海野チカはそれにプラスして一時間の才能だと語る、一万時間+一時間。一万時間はやってみるしかない、考えるより前に行動だと、しかし、それで何もなかったとしても+1時間が重要だということだ。なぜか?
「そこまでいけばやめられなくなるから」
という恐ろしい理由だ。そしてここからさらに新しい一万時間の壁が出てきたとき、それにむかってさらに進む力、そういう偏執狂的なものが才能なのではないかと話す二人、だから才能云々について西尾維新は才能があると信じるふりをするのも重要だという。
そこまでして書くことの意味は何なのか、そのモチベーションについて彼はこう言う。
西尾維新「十年後の自分が面白いと思えるようになることですね。十年生きるモチベーションになります」
そう西尾維新にとって生きることと書くことは本当に等価なのだ。
少しカウンセリングのような趣がある芥川賞作家、堀江敏幸との対談で彼は西尾維新を「配分しない、空っぽにする」書き手であると評す。
ということは空っぽにした後に再び満たすため、インプットもかなりやる必要がある。ここにきて連続して行われた対談の意味がようやくわかる。この本は西尾維新が生きる=作るということを続けるべく、自分がファンであり信頼している創作者に疑問をぶつけ、そこから出てきた言葉の数々を貪欲に摂取していくためのもの。
さらに走り出すために、おそらくはもっと書けるはずだという信念から。
そして、それは対談相手もおそらく同じである。皆が一様に西尾維新との対話を通じてモチベーションを獲得しているように思う。だからこの中に出てくる人物のファンならば、彼らが具体的な創作物からどういう着想点で物を語っているか、そのヒントとなるものがとにかく多く必読の本である。
ちなみにこの原稿の文字数が単純計算で約3000字、一日20000字を毎日。ああ、おそろしい・・・!
【関連記事】
関連記事
-

-
女性器サラリと言えますか?『私の体がワイセツ?!女のそこだけなぜタブー』(ろくでなし子、筑摩書房)感想
検索結果の順位が下がったり、サイト全体の評価が下がったりとそういうことで、グーグ …
-
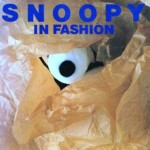
-
スヌーピー95変化!貴重な写真集『スヌーピーインファッション』(リブロポート)
ずっと見たかった『スヌーピーインファッション』をようやく入手。 ええ、たまらなく …
-
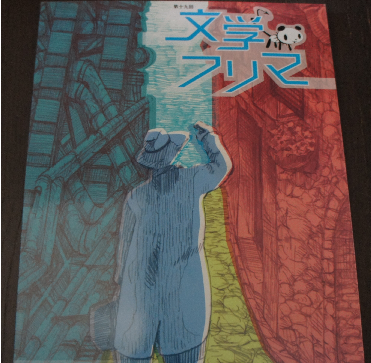
-
「第十九回文学フリマ」へ行って買ってつらつら思ったこと
11月24日(祝)に行われた「第十九回文学フリマ」に行ってきました。前回行ったの …
-

-
ビジネス書中毒に注意せよ!『読書で賢く生きる。』(ベスト新書)感想
中川淳一郎・漆原直行・山本一郎という著者の名前がなければ『読書で賢く生きる。』と …
-
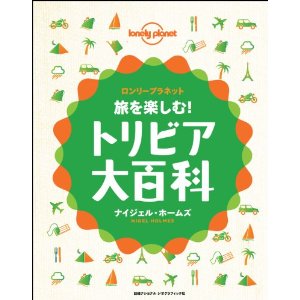
-
旅を本当に楽しむための本『旅を楽しむ!トリビア大百科』
一時期、「1秒間」に世界ではどんな出来事が起きているかという広告が電車内に掲載さ …
-
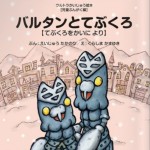
-
名作+怪獣+ウルトラマン=「ウルトラかいじゅう絵本」のカオスな物語たち
ウルトラマン×絵本といえば思い出すのは、子育てに奮闘するウルトラマンやバルタン星 …
-

-
人類を存続させる思いやり『中原昌也の人生相談 悩んでるうちが花なのよ党宣言』(中原昌也、リトル・モア)感想
「中原昌也」の「人生相談」、タイトルの段階でこの本は面白いに決まっているが、最初 …
-
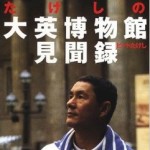
-
【書評】ビートたけしVS大英博物館『たけしの大英博物館見聞録』(新潮社・とんぼの本)
現在、東京都美術館で「大英博物館展―100のモノが語る世界の歴史」が開かれている …
-
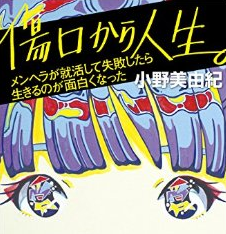
-
武器を理解せよ傷を理解せよ、小野美由紀著『傷口から人生』(幻冬舎文庫)書評
本の正式名称は『傷口から人生。メンヘラが就活して失敗したら生きるのが面白くなった …
-

-
面白いインド映画を探すならこの本!『インド映画完全ガイド』
踊らない、そして伏線を巧みに利用した洗練されているインド映画が増加中である。 た …

