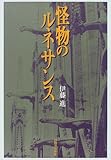実写版『ブギーポップは笑わない』を見て感動した人と友達になりたい
2015/11/26
時代の空気をまとった映画について最近考えている。
たとえば、「スプリガン」「地獄の警備員」「ガメラ3」「エコエコアザラク」と適当に羅列してみる。間違いなくこの作品を支える想像力は時代の空気によってもたらされたのだと根拠もなく自分は思う。
それは「世界には謎がある」という確信だ。
この世界の背後には何かが隠されている。それが世界の終末をもたらし、気づいているのは何人かだけ。その磁場からいずれおそるべき暴力が噴出する、ノストラダムスの大予言があそこまで信じられたのもおそらく、このような想像力が一番活性化されていた時代だからだ。
構造だけ見ると2000年代、正体不明の存在が平凡な日常に侵犯する物語を持つ「セカイ系」と呼ばれるものに近いような気はする。しかし、その場合は「彼女」という媒介が強く前景に現れており、さらにオカルト的な要素や禍々しさは90年代に比べ薄まった印象がある。
さて、こんなことを考えているのも、映画『ブギーポップは笑わない』がまさに90年代の空気をベッタリとこべりつけていたからだ。
『ブギーポップは笑わない』とは
映画が公開されたのは2000年3月11日だが、原作は1997年に第4回電撃ゲーム小説大賞において大賞を受賞した上遠野浩平の小説である。
KADOKAWA / アスキー・メディアワークス
売り上げランキング: 3820
物語の構成は高校で起きた連続生徒失踪事件に対して登場人物が様々な角度から証言していく(時間も前後する)ことで、徐々に事件の全容が明らかになっていく形式だ。事件の真相を知るのは最後まで物語を読み終えた読者と、登場人物すべての証言に現れる黒い帽子に奇妙な服を着た死神とも称される「ブギーポップ」(=不気味な泡)という謎の存在だけである。
その正体は事件が起きた学校と同じ高校に通う女子生徒である宮下藤花。ブギーポップは世界の危機があらわになった時に彼女の無意識化から現れ「世界の敵」と戦うことを使命としている。無意識の主題も実に90年代という感じもするが、面白いのは登場人物のほとんどが何かしらかの不全感を抱えていることだ。
そして映画『ブギーポップは笑わない』
ハピネット・ピクチャーズ
売り上げランキング: 69724
不全感とは、どこにも到達できない感覚である。エコーズと呼ばれる別次元の存在と怪物マンティコアの戦いに巻き込まれたことが連続失踪事件の真相とはいえるものの、「彼ら」の詳しい正体については原作小説の別のシリーズで語られる。
つまり本作においてその正体はさして重要ではない。
重要なのは映画のキャッチコピー「あした、死ぬかもしれない」が暗示するように、世界に危機をもたらす存在への登場人物たちの漠然とした認知と日常がふと終わるかもしれないことへの思いである。彼らはその「何か」に気づいていながらたどり着けない、ブギーポップ以外でその場所に近いところまで到達しているのは自らを「メサイアコンプレックス」と称し「正義の味方」であろうとする「炎の魔女」霧間凪という女生徒だけ。
その意味において対照的なのは末真和子という生徒の存在だ。彼女は偶然エコーズとマンティコアの飛び立つ光を部屋でひとり目撃してしまう。

非日常が、わたしの平凡な日常を飛び越えてゆく情景を見て彼女は言う、「事態はいつも、私の横を素通りする」と。世界の中の断片たることを自覚している彼女にとっては、非日常の物語を後からしか観測できないという諦念のようなものがある。だからこそ全ての自体の中心にいる霧間凪に憧れを抱くのだ。
映画の中で登場人物の一人、竹田啓司が『怪物のルネサンス』という本を読んでいる点も興味深い。物語的にはこの小道具で異形の存在マンティコアを予告しており、より詳しく見るならば、本書で書かれている内容は、中世ヨーロッパにおいて怪物は身近な存在として様々な目撃情報があり、その意味するところは怪物とはある種の災厄を予知する存在であったということだ。そして文献において怪物の目撃情報は世紀末において増殖するとも。
そのような世紀末を迎えているのに、自分のもとには何も起こらない、もしかしたら物語が進行しているかもしれないのに全ての物語を観測することはできない。その焦燥感と自分自身の将来への不安を映画は上手く表現していた。
特にロケーションである。ニュータウン特有の整然と植えられた植物と人工的なつるつるした歩道、そこを歩く人物たちをロングショットで撮影していく。それによって登場人物ですら世界の一員に過ぎないという強い印象を受ける。また批判されている俳優たちの棒のような演技には青春の気怠い感じがはからずも出ている。

「世紀末」にはおそらく人の不安を増長させる何かがあり、その漠然とした危機が「怪物」となってあらわれてくるのだろう。平凡な日常を飛び越える非日常への憧れ、そのこと自体は青春の何物でもない時期において普遍的に感じる思いではあるが、90年代はそこにオカルトが接続されていたのだと自分は思う。
その空気を実写版『ブギーポップは笑わない』は的確に表現しており、今では「中二病」と片づけられる想像力が、ネタとしてではなくマジに語られていることに羨望を感じてしまう。
好き嫌いはハッキリ別れ、意味わからないという人もいると思う。けれど、この文章を見て「何か」に感づいたのなら是非この映画を見てほしい。
そしてそこに懐かしさを感じた人と是非とも友だちになりたいと心から思う。
【関連記事】
関連記事
-

-
鈴木亮平&井上真央の声に心震える教養映画『ルドルフとイッパイアッテナ』感想
2か月ぶりの更新でごわす。 2か月も更新してないと「大丈夫か」などの声も聞こえて …
-

-
映画『PAN ネバーランド、夢のはじまり』感想。2015年屈指の3D表現に痺れた
黒ひげ:「ネバーランドへようこそ!」 最近定型の物語を脚色したり、後日譚を作った …
-
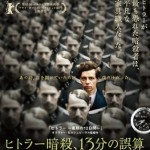
-
『ヒトラー暗殺、13分の誤算』感想、変わりゆく世界に一人の男が願ったもの
1939年11月8日 この日、ミュンヘンのビアホールで演説をしていたヒトラーは講 …
-

-
文化を支える矜持、フレデリック・ワイズマン新作『ナショナル・ギャラリー 英国の至宝』
この作品のことだけを考えていれば他の見なくてもしばらくやっていける。そう思わせて …
-
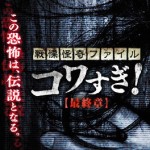
-
【映画感想】すべての終わりの目撃者となれ!『戦慄怪奇ファイル コワすぎ!最終章』
(ネタバレしかない) GWはずっと白石晃士監督作の映画を連続鑑賞。そして最終日に …
-

-
映画『I LOVE スヌーピー THE PEANUTS MOVIE』の前におさらい劇場版スヌーピー
劇場版『I LOVE スヌーピー THE PEANUTS MOVIE』がいよいよ …
-
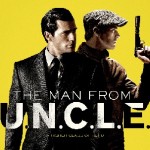
-
映画『コードネームU.N.C.L.E.』感想、どこから切っていってもガイ・リッチー
なんだかスパイ映画が多かった2015年の末尾に公開された『コードネームU.N.C …
-

-
並大抵のホラーじゃ太刀打ちできない『映画クレヨンしんちゃん伝説を呼ぶ!踊れアミーゴ!』のヤバすぎる怖さ
自分が「書く」行為にいたるときは、いやいや過小評価され過ぎでしょう、おかしいでし …
-
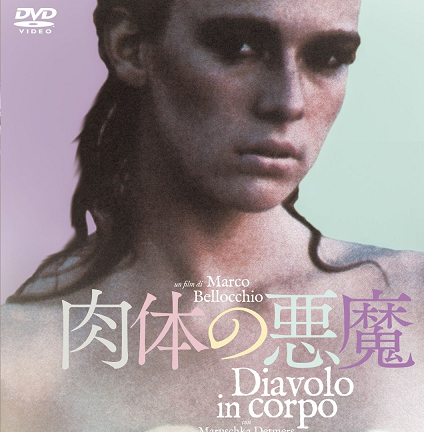
-
マルコ・ベロッキオ『肉体の悪魔』映画評
「テーブルクロスはもとの所に戻しなさい 悲しげな死者たちが、やって来るから」 「 …
-
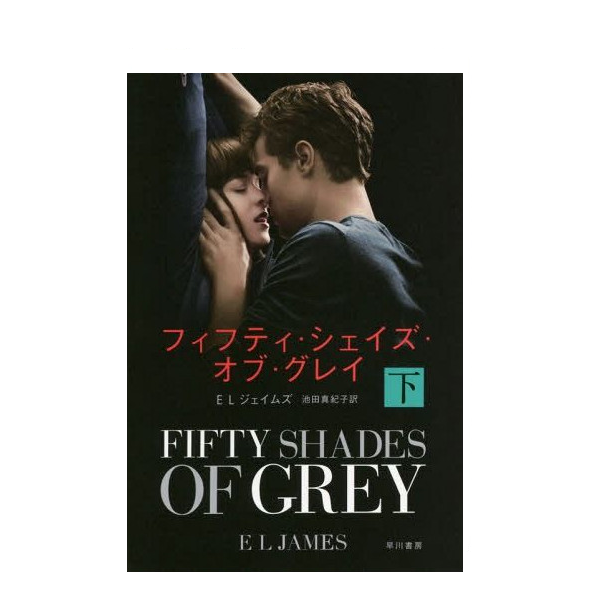
-
映画『フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ』雑記(ネタバレあり)
グーグル広告の基準でいえば、アダルト系の文章はあまりおススメはしませんよ、とのこ …


![ブギーポップは笑わない [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51iXsHsbvJL._SL160_.jpg)