寝る前にアントニオ・タブッキ『夢の中の夢』(岩波文庫)を読む
2015/11/26
読書日記をつけてみることにしました。まずは一冊目として
タブッキ『夢の中の夢』について書き、眠ることに。
アントニオ・タブッキによる序文。
「自分の愛する芸術家たちの夢を知りたいという思いに幾度となく駆られてきた。(中略)文学の力をかりて、その失われたものたちを補うことで、なんとかそれを埋め合わせてみたいという誘惑はおおきい。もちろん未知の夢にあこがれる者が想像力でつくりあげた身代わりの物語が、貧弱な代用品にすぎないことも、あわい幻想が生んだ招かれざる夾雑物でしかないことも承知している。願わくば、これらの物語があるがままに読んでもらえますように、そして、いまは彼岸で夢見ているわたしの人物たちの魂が、かれらの末裔に寛大でありますように」
この本に出てくるかれらとは20人、ダイダロス、オウィディウス、アプレイウス、アンジョリエーリ、ヴィヨン、カラヴァッジョ、ゴヤ、コールリッジ、レオパルディ、コッローディ、ステーィブンソン、ランボー、チェーホフ、ドビュッシー、ロートレック、ペソア、マヤコフスキー、ロルカ、フロイト・・・。見ただけで心が躍る名前もあればチェッコ・アンジョリエーリという馴染みのない名前も見受けられる。
この本は彼らの人生に影響を与えたであろう一夜をタブッキが綿密な資料をもとに切り取ってその夢を追想するといった形式の作品である。そして、これが評伝でも物語でもないとっても不思議な一冊となっている。
一篇一篇は短く楽しみながらサラリと読めるが、それ以上に読み込めば読み込むほど面白くなるのがこの本の厄介さであり心躍ることだ。タブッキが敬愛する芸術家の夢を描くためその人物に関する資料を丁寧に読み込んでいることがわかる、つまり輪郭を補強することで夢という空想にギリギリの肉薄をしているのだ。例えば、フランソワ・ラブレーがパンダグリュエルと食物をお腹いっぱい食べる夢の冒頭はこう書かれている。
「一五三二年二月のある晩のこと、リヨンの病院で作家にして破戒僧、フランソワ・ラブレーはある夢を見た。修道会をはなれてからも習慣としてつづけている規則に則って七日間断食したあと、かれは病院の質素な自室で眠りについていた」
- ・一五三二年二月・・・ラブレーが『パンタグリュエル物語』を出版した年。
- ・リヨンの病院・・・この年に医師として正式に勤務。
- ・破戒僧・・・10代の後半で彼は修道院を出て放浪の旅に
- ・規則に則って七日間断食・・・彼が生み出したパンダグリュエルは逆に大食漢
ある一人の夢の冒頭からしてこの密度である。なぜここまで厳密に構築しているかという問いに例えば、訳者の和田和彦氏はこの物語を「夢」という自閉的な物語を読者に開いていくための「一分の隙もない仮構の構築」と評している。私はこれをこう考えた、あるがままの夢、それは確かに面白いがそのままそれを描いても、そこには独りよがりのイメージ群が連なっているだけだということだ。
つまり夢を他者へと開いていくためには、イメージを成り立たせるものへの分析が必要だということ。私たちがこの夢物語を持って彼らが残した夢の結晶である残された作品に照射すること、その光がまたこの夢物語を照射することで物語に新たな読みの可能性が加わる、これが「夢の中の夢」ということなのだ。
たとえばフェルナンド・ペソアにとって一九一四年三月七日がいかに重要な日だったのか、奇跡的に残された作品から現在の私たちは知ることが出来る。現実のように夢を生き、夢のように現実を生き現実を複数化させた詩人フェルナンド・ペソアはこのテクストの冒頭、夢の中で目覚め彼の中で大きな比重を占めることになる師でもあり、もう一人の自分であるアルベルト・カエイロに出会う。「きみはわたしの声に耳をすませばいい」という託宣を受けた後、彼に別れを告げると「夢の終点」まで連れて行ってくれるようペソアは御者に頼む。目覚めのシーンはなく、彼の部屋に陽光がさすところで物語は終わっている。
現代最大の詩人とは、夢の能力を最大に備えている人物のことだろう。
ペソアの200の言葉の引用からなるタブッキ著『詩人は変装の人』より
ペソアは彼と異なる人格を作りだし、彼ら(アルベルト・カエイロ、リカルド・レイス、ベルナルド・ソアレスなど)といういわば虚構をもって現実を生きた。現実と夢を二項対立で語るのではなく溶けあわせること、そうしたペソアの資質がこの物語において構築されている。夢をもって夢を見ること、「夢の中の夢」、この書物の終わりは「他人の夢の解釈者 フロイト博士の夢」で終わっている。分析する患者である女性ドーラにフロイト自身が夢の中で変化してしまうという読みとく対象との同一化のお話である。
【関連記事】
関連記事
-

-
映画館はつらいよ『映画館のつくり方』(映画芸術編集部)
映画好きなら1度は考えるかもしれない。 「映画館を運営するということ」 しかし、 …
-

-
『怪談短歌入門』書評~怖さには構造がある、短歌篇~
Contents0.0.1 1 陰翳礼讃、隠すことの美学2 定型詩には、隠すこ …
-

-
【書評】家庭科を食らえ!『シアワセなお金の使い方 新しい家庭科勉強法2』(南野忠晴、岩波ジュニア新書)
「ああ学生時代もっと勉強しとけば良かった」 こんな言葉に巷で良く出会う。「どの教 …
-

-
上野千鶴子に映画の見方を学ぶ『映画から見える世界―観なくても楽しめる、ちづこ流シネマガイド』感想
数年前に新宿シネマカリテで、レオス・カラックス監督の映画『ホーリーモーターズ』を …
-
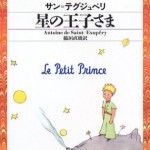
-
映画『リトルプリンス星の王子さまと私』を見る前に再読しませんか原作
2015年11月21日に公開される映画『リトルプリンス星の王子さまと私』は、とあ …
-
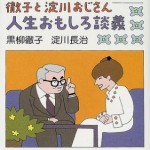
-
【書評】人生の圧倒的な肯定感に満ちた本『徹子と淀川おじさん人生おもしろ談義』
とにかく元気に二人は話す。 「徹子の部屋」に出演した淀川長治と番組パーソナリティ …
-
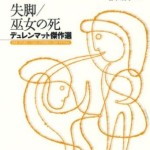
-
デュレンマット『失脚/巫女の死』より「失脚」評
デュレンマット『失脚/巫女の死』より「失脚」のあらすじ 失脚/巫女の死 デ …
-
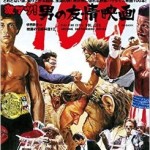
-
【書評】読んで燃えろ、見て燃えろ『激アツ!男の友情映画100』(洋泉社・映画秘宝EX)
【友人として、相手を思い、また裏切らぬ真心】とは「新明解国語事典第6版」に記載さ …
-
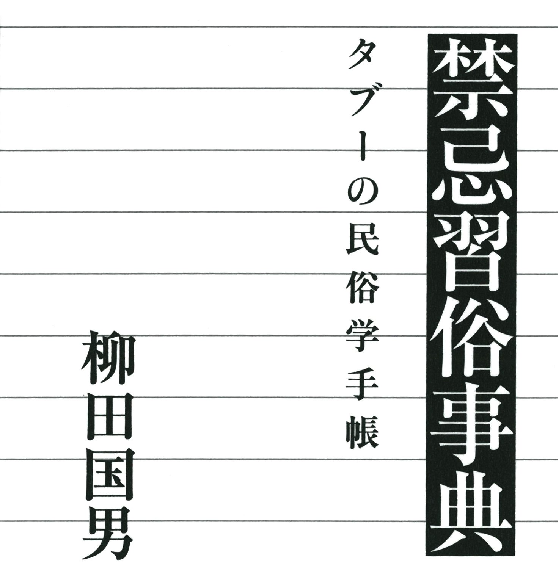
-
~禁忌への想像力~柳田国男『禁忌習俗事典 タブーの民俗学手帳』(河出書房新社)評
タイトルにつられて購入。「禁忌」と聞いて右目が疼く。 しかし事前に想像していたそ …
-
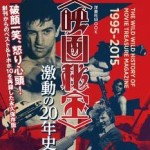
-
This is eigahiho!『<映画秘宝>激動の20年史』 (洋泉社MOOK)感想
タイトルは『300』的なノリで。 現在も大々的に刊行されている映画雑誌といえば『 …


