上野千鶴子に映画の見方を学ぶ『映画から見える世界―観なくても楽しめる、ちづこ流シネマガイド』感想
2015/11/27
数年前に新宿シネマカリテで、レオス・カラックス監督の映画『ホーリーモーターズ』を鑑賞後、頭が混乱した。その戸惑いを抑えるべく壁に掛けらていた映画評を見ていたら、難解な修辞学に逃げることなく映画の流れや構成を明晰に語っている文章に出会い、しばし時間を忘れて読みふけった。
評者に「上野千鶴子」とあって驚いた。あ、上野千鶴子って映画評も書くんだと。
それからしばらくたってこの本が出た。2008年から2013年に「クロワッサン・プレミアム」で連載していた性質のため、俳優や映画のテーマ、それについての自身の感想などがコンパクトにまとまっており大変に親切な作り。ちなみに『ホーリーモーターズ』評もここで読むことが出来る。
どうやら上野先生、昔はかなりの映画フリークだったようだ。若い頃は三本立ての上映やオールナイトで朝まで、というようなこともやっていたらしく勝手な親近感が湧いた。
だから編集者の依頼で久しぶりに映画について考えるようになって、「わざわざ映写機を購入し、壁面にスクリーンが降りてくるようにしておうちにミニシアターをつくったりもした」と実に楽しそう。
さて、楽しみながら書いている筆さばきであるが上野千鶴子はフェミニズムの論者として「辛口」で知られている。(知らない人は『東大で上野千鶴子に喧嘩を学ぶ』を読んで震えよう)
映画ではどうだろう、もちろん。納得がいかないと容赦なく斬っていく。
たとえば『ヒステリア』という19世紀末ロンドンを舞台にした女性用バイブレーターを発明した男の映画がある。
女性のヒステリーを性的欲求の解消、つまり「性的マッサージ」によって治していた青年医師が働きすぎによって腱鞘炎になってしまい、しかしそれによって電動マッサージの開発へと繋がるという脚本の流れが巧みで、間には当時のイギリスが抱えていた女性の権利の問題が絡む。
「ああ・・・いい話や」と見終わって普通にそのままべた褒めしている感想が当時の自分のノートに書いてあった。小道具もいいし、ほんわかした終わりが好みだと。
だが女性の権利活動をしていたヒロインが、最後に主人公と結ばれるラストが上野千鶴子は不満らしい。
「バイブは男要らずのはずなのに、対等なパートナーを求めたヒロインに、最後にビクトリア調の求婚が待っている。やっぱりロマンスと結婚が終着駅なのか。夫と違ってバイブなら、合わなきゃすぐにとっかえられるのにね」
とこんな感じで上野節が炸裂する。そう言われると、確かに後半の展開は甘々である。自分はその甘々が良いと思ったが、しっかりした軸のある意見は聞いていると参考になり、映画のテーマについて今一度振り返る行為、つまり対話が生まれるきっかけとなる。
テーマが明快にあって、それを理解していても語りにくい映画がある。「映画批評」といったときに、ともすればそうしたことから目を背け、何が画面に映っているかといった美学的側面へ逃避してしまいがちだが上野千鶴子はテーマから目をそらさない。映画が何を伝えているかという「軸」を彼女はしっかり捉えていく。本書の目次は「老い」「女性の生き方」「戦争」など語りづらいものばかりである。
たとえば「老い」というテーマ。その老いについて、何を語っても具合の悪い感覚に満ちた文章になるのは想像がつくので映画にそれが描かれていた場合、そこを自分は迂回することが多い。経験がすべてとは言わないが、語りづらい作品に出会った時に語りやすい側面を見つける傾向が自分にはあると気づかされた。しかし上野千鶴子はミヒャエル・ハネケ『愛、アムール』を老齢の男女の問題としてのみ描くテーマを批判する、行政や制度について描かなくていいの、と。
それに反論することは出来る。その世界の狭さ、金を持っていても追いつめられることの苦悩、たとえ監督本人がそう思ってないにしても(そう思ってない節はある)『愛、アムール』というタイトルは皮肉だと自分は捉えたということを。
けれど、この意見はこの本を読むまで考えつかなかった。無意識の内に正解を求めてしまい、それについてのテーマに対して自分の経験が足りないと、馬鹿なことを言いそうだと、この映画の場合は作品に出てくる部屋の狂った構造について思考し「老いと介護」に真っ向勝負で答えなかった。
語りづらい映画について、しっかりとそのテーマが描かれているのならそれに答えることもまた時に必要なのだ。たとえ間違っていると言われても、しっかりと軸をもってした言葉はさらなる意見の可能性となる。上野千鶴子の映画評にはそれがあり、それは当然映画以外の所から調達してきた彼女の戦いの成果である。
そういう人だからこそ、原発事故を描いた園子温の『希望の国』を、真正面から受け止めた上でその試み自体は評価しつつも「ホンモノの悲劇には届かない」と言えるのだ。2008年~2013年の5年間に「日本」で上映された作品について語ったこの本は、コンパクトな映画評でありつつ、上野千鶴子が見た社会が投影された貴重な時評集でもある。
【関連記事】
関連記事
-
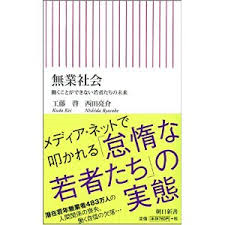
-
工藤啓・西田亮介『無業社会』評~根性論からの脱却~
朝日新書『無業社会』工藤啓・西田亮介(著)を読みながら、他人事じゃないという強い …
-
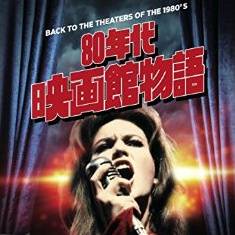
-
ゆきゆきて80年代、斉藤守彦『80年代映画館物語』(洋泉社)書評
「1980年代の東京」 そこは当時を知ってる人の言葉でいうならば「世界中の映画が …
-
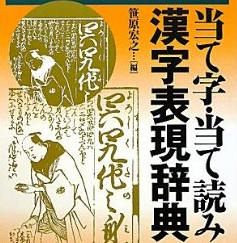
-
運命は「さだめ」な笹原宏之編『当て字・当て読み漢字表現辞典』(三省堂)
今日紹介するのは「妄想型箱舟依存型症候群」と書いて「アーク」と読むサウンド・ホラ …
-
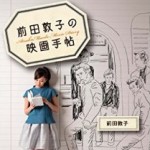
-
【書評】初々しい言葉の連なり『前田敦子の映画手帳』(前田敦子・朝日新聞出版)
映画を見ないとその日は落ち着かないくらい、いま映画にはまっています。一日に何本も …
-

-
デアゴスティーニ『隔週刊 映画クレヨンしんちゃん DVDコレクション』の刊行順にオトナの匂い
最近、書店で見かけてちょっとビックリしたのがデアゴスティーニから刊行された「映画 …
-
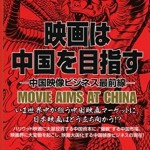
-
【書評】『映画は中国を目指す』(洋泉社・中根研一)
「アイアンマン3」「ダークナイトライジング」「パシフィック・リム」・・・近年のハ …
-
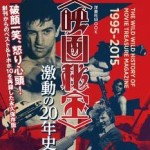
-
This is eigahiho!『<映画秘宝>激動の20年史』 (洋泉社MOOK)感想
タイトルは『300』的なノリで。 現在も大々的に刊行されている映画雑誌といえば『 …
-
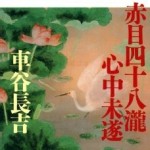
-
【私的印象批評】底を求める/書くことの業『赤目四十八瀧心中未遂』(車谷長吉、文春文庫)
車谷長吉の直木賞受賞作『赤目四十八瀧心中未遂』は、主人公である「私」が数年前に地 …
-

-
反スペクタクルへの意志『テロルと映画』(四方田犬彦・中公新書)感想
映画は見世物である。激しい音や目の前に広がる大きなスクリーンによって人々の欲望を …
-

-
懐かしいが懐かしいが懐かしい『念力ろまん (現代歌人シリーズ) 』(笹公人・書肆侃侃房)感想
たまたま手に取ってグイと魅了されたこの笹公人の『念力ろまん』は、ただ単純に短歌を …


![ヒステリア [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51i9TmW0BgL._SL160_.jpg)
![愛、アムール [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51DhY9eCdnL._SL160_.jpg)