【書評】皿々に召還せし、人々の記憶『ラブレーの子供たち』(四方田犬彦・新潮社)
2015/11/27
流石新潮社、豪華だわ…と思いながら四方田犬彦『ラブレーの子供たち』を読み進めた。
最近、豪華な料理とはそもそもどういうものか?と考えることがよくある。特定の場所でしか手にに入らないもの、金を積んでも食べられない地産地消の食品等、そこには様々な観点があり、めちゃくちゃ高価なものが即、豪華さとイコールで結ばれるわけではないように思う。
そんな風なことをつらつら考えていたからこの本の視点に自分は実に興奮した。作品に出てくる料理を再現した書籍は数多くあるが、この料理エッセイは様々な古今東西の有名人物が偏愛していた料理を現代日本において再現するものというものなのだ。
そこからいったい何が見えてくるか。
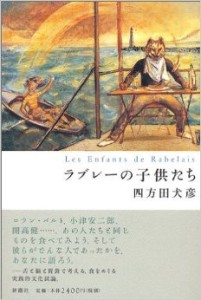
「どんなものを食べているか言ってくれたまえ。君の人となりを、言い当ててみせよう」
この『美味礼賛』の著者サヴァランの言葉が冒頭にあるとおり、ある人が繰り返し食べていたり、またはチラっとしか言及してない料理を著者が実際に作って食べることで、それらがその人にとってのある重要な思想を内包しているのでは?ということを思索していくのである。
堅苦しい本ではない。それこそ取り上げられるメニューがロラン・バルトの『表徴の帝国』についての記述から始まるように筆は軽やかだ。天ぷら油の処女性について論じ、すき焼きこそ理想的な前衛さを兼ね備えてるというバルトの視点は真実かどうかよりも、思いもよらない考えを提示してくれる点でこの本と似ていた。
例えば立原正秋である。日本酒や古寺について造詣が深く、流麗な文体を使いこなし日常生活においては鎌倉に居を構えたこの文士に著者は苦手意識を持っていたようだ。
しかし彼が晩年、山中で山菜を取り、それを蒸して包む料理を好物にしていたという記述から、立原正秋が鎌倉に住んだのは無意識の内に韓国で生まれた幼き貧乏の時代を回想する思いがあったのではないかと著者は認識を改める(食材を葉物で包む作法は韓国料理の伝統の一つ)
または澁澤龍彦。彼が幼少期に好んで食べた「ある食べ物」に政治や戦争に関してあまり語らなかった人の戦争観が現われているのではと著者は見立てる。その食べ物こそ真ん中に白いコンデンスミルク、その周り全てにジャムを敷き詰めた「反対日の丸パン」である。それはひたすら甘く、食べるのものを快楽で満たす。
だが普通の日の丸パンではどうか。真ん中にジャムを塗るだけ=ジャムの分量は少ない=快楽の量が少ない。ここから「日の丸」を忌避する澁澤龍彦の心性は案外このように徹頭徹尾彼の快楽原則に反しているからではないかという直観は読んでいるとゾクゾクして楽しい。
ラフカディオ・ハーンの作っていたクレオール料理や古代ローマの子豚の丸焼きの再現など「一度は食べてみたい。豪華だ…」と思いつつも、一番面白く豪華であるのは敗北があらかじめ予見されている料理である。
アンディ・ウォーホルが題材にしたキャンベルスープ缶をひたすら取り寄せて飲んでみて、その味付けの均一性にうんざりしながらもそれが実にウォーホルのテーマのようだと感心したり、またはイタリア未来派の料理作法を忠実に再現してみせたりする。料理を芸術にするために彼らは視覚的要素こそ重要だと考えていたので、著者も手を青くし(流石に手袋着用、本来は塗料使用)、照明を変化させ室温を急激にあげたりして未来派が捉えた「イタリア」料理を作り上げる。
ある意味で馬鹿馬鹿しい行いだが作り上げたコースには美しいイタリアという赤・白・緑という価値観が内包されており、そこに政治的な芸術へと変容した未来派の萌芽が見られるという感想が秀逸だ。
無駄かもしれず・失敗するのもわかっていながらも試しにトライしたことで出来たものが何らかの新しい知見を引きだし知的快感へと繋がることもある。つまり、おそろしいほどの手間をかけて美味くはないものを作り上げること、それもそれで「豪華」な料理であるとこの本は教えてくれる。
ちなみに本の目次(お品書き)はこんな感じである。
・ロランバルトの天ぷら
・武満徹の松茸となめこのパスタ
・ラフカディオ・ハーンのクレオール料理
・イタリア未来派のお国尽くしディナー
・立原正秋の韓国風山菜
・アンディ・ウォーホルのキャンベルスープ
・明治天皇の大昼食
・ギュンター・グラスの鰻料理
・谷崎潤一郎の柿の葉寿司
・ジョージア・オキーフの菜園料理
・澁澤龍彦の反対日の丸パン
・チャールズ・ディケンズのクリスマス・プディング
・『金瓶梅』のカニ料理
・マリー=アントワネットのお菓子
・魔女のスープ
・小津安二郎のカレーすき焼き
・マルグリット・デュラスの豚料理
・開高健のブーダン・ノワールと豚足
・アピキウス古代ローマの饗宴
・斉藤茂吉のミルク鰻丼
・ポール・ボウルズのモロッコ料理
・イザドラ・ダンカンのキャビア食べ放題
・吉本隆明の月島ソース料理
・甘党礼賛
・四方田犬彦のTVフリカケ
【関連記事】
・書評『田中小実昌エッセイ・コレクション3「映画」』食べて、見終えて、酒飲んで
関連記事
-
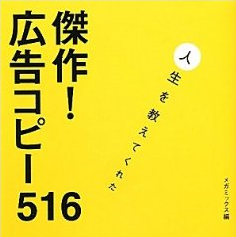
-
傑作の影にクソもあり、メガミックス編『傑作!広告コピー516』(文春文庫)書評
「需要が違うんだから」と女性に言い放つクソ男の台詞とその的外れなダサい広告のせい …
-

-
デッドプールの大好物「チミチャンガ」簡単レシピ。圧倒的美味さに快楽度MAX
6月に日本で公開される『デッドプール』の予告編を見ていたら、このろくでもないヒー …
-
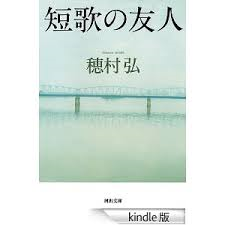
-
穂村弘『短歌の友人』書評~友達作りの方法論~
「俺にもできる」 短歌を作ろうと思ったのは1年ぐらい前に読売新聞を読んでいた時だ …
-
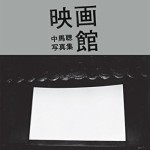
-
見る人の記憶をこじ開ける写真集『映画館』(中馬聰、リトル・モア)
あまり映画を見ない家族のもとで育ったので、映画を本格的に見始めた時期は人より遅い …
-
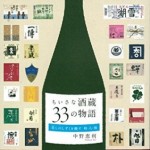
-
【書評】『ちいさな酒蔵33の物語』(中野恵利・人文書院)を読んで微生物に思いをはせる夜
ブームを受けて日本酒の本が最近多数出版されているが、本書は酒蔵自体にスポットの当 …
-
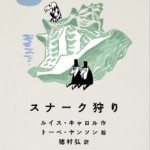
-
【書評】キャロル×ヤンソン×ホムホムの『スナーク狩り』(集英社)はプレゼントに最高の一冊
「不思議の国のアリス」の作者ルイス・キャロル原作! 「ムーミン」の作家トーベ・ヤ …
-
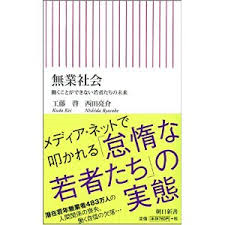
-
工藤啓・西田亮介『無業社会』評~根性論からの脱却~
朝日新書『無業社会』工藤啓・西田亮介(著)を読みながら、他人事じゃないという強い …
-

-
嗚呼、ややこしきハラールよ『ハラールマーケット最前線』(佐々木良昭)書評
(内容が厄介なだけに長文です。すまん) Contents1 バンコクで出会った「 …
-
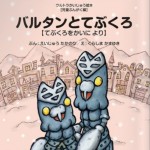
-
名作+怪獣+ウルトラマン=「ウルトラかいじゅう絵本」のカオスな物語たち
ウルトラマン×絵本といえば思い出すのは、子育てに奮闘するウルトラマンやバルタン星 …
-

-
人類を存続させる思いやり『中原昌也の人生相談 悩んでるうちが花なのよ党宣言』(中原昌也、リトル・モア)感想
「中原昌也」の「人生相談」、タイトルの段階でこの本は面白いに決まっているが、最初 …

