【書評】家庭科を食らえ!『シアワセなお金の使い方 新しい家庭科勉強法2』(南野忠晴、岩波ジュニア新書)
2015/11/27
「ああ学生時代もっと勉強しとけば良かった」
こんな言葉に巷で良く出会う。「どの教科?」と話を続けると『数学』とか『英語』という答えが返ってくることが多い。
そんなとき「家庭科はいかが?」と勧めたくなる、そういう思いを抱かせる本だった。
そもそも「家庭科」とは?
『大辞林』で調べるとそもそもの意味として「家庭科」とは「家庭生活に必要な知識・技能・態度の習得を目的とする」学問のことらしい。
しかし一般的に「家庭科」と聞いて思い浮かぶイメージは何だろう。
自分の場合、ミシンの使い方だったり、なんかみんなで一緒に頑張った調理実習だったりと実習的な要素ばかり記憶に残っていて知識的なことや「家庭科」という学問の位置づけなんぞはほとんど覚えていない。普通科だと大体そんなもんじゃないかしら。
お金にクローズアップした本書
正しいパンツのたたみ方――新しい家庭科勉強法 (岩波ジュニア新書) ↑この素晴らしいタイトルの前作でも若干述べられていたが、今回取り上げる本は「お金」という分野をクローズアップして「家庭科」について学ぼうというもの。テーマは一つ。「見えるお金」と「見えないお金」を適切に区別し、お金と自分との関係を考えましょうということだ。
「見えるお金」は何となくわかりやすい。いわゆる「可処分所得」、自分が自由に使えるお金である。しかし「見えないお金」とは?
「見えないお金」を見えるようにするためここで取り出されるのは「給与明細」だ!(岩波ジュニア新書、子供向けだろうが誤魔化さない!)
そこに書かれている「住民税」「所得税」「介護保険料」などの項目こそまさに、この社会を維持・安定させるための「見えないお金」であると著者はジックリ丁寧に解説してくれる。(「可処分所得」の中でも消費税や公共料金はその考えに基づいている)
社会は自分以外のお金で回ってるというのは当たり前の考えである。けれど、その見えにくい「お金」の仕組みを明らかにすることで自らの「ライフスタイル」は自分がどう選択していくかだけではなく、どういう国(状況)に住んでいるか等に大きく影響されるのがわかる。
ツラすぎる!「私の大切なもの」ワーク
膨大な見えづらい情報について鋭敏になり自分は何を大切に思っているのかを把握することこそ、仕組みと自分との距離を適切に測ることへと繋がり、自らの「ライフスタイル」を考えることが出来ると著者は言う。
そういうバランスのとれた「目利き」となるための第一段階として、本書では「あるワーク」が推奨されるのだが・・・これが実にキツい作業だった(笑)
笑いながらやっているうちに、真顔となり最後は苦悶の表情となる、詳しくは本書を読んでやってみてほしいが、(ネタバレになるからね)
自分の大切なものが「寛容さ」という結論に至った時、表面的な納得ではなく深いところで考えさせられるものがあった。「これは凄い」とためしに知り合いにやらせたところ、相手は「学び」となって、現在悩んでいる頭のモヤモヤが少し晴れたらしい。
このワークを通して頭をひねる作業、今のところ2015年で一番悩んだ本である。
「家庭科」とは社会のしくみを「家」から理解すること
金を使う楽しみを知れば知るほど、それが習慣となってしまい、お金をどうやって増やすかということに目が向きがちだ。
しかし、内田樹・岡田斗司夫『評価と贈与の経済学』、西原理恵子『この世で一番大事な「カネ」の話』、荒川弘『百姓貴族』など話題となったお金に関する書籍を参考文献としているこの本は、まず一度立ち止まって自らのライフスタイルを確認することで物事は色々とスムーズに進むのでは?ということを教えてくれる。
「家庭科」はそう見ると「政治経済」の経済分野に近づいていくが、どちらかと言うとシステム的な方面からというよりも身近な家という概念を手掛かりに社会のしくみを見ていく学問と言えるだろう。「家庭科」が持つ重要な意義と面白さを存分に実感させてくれて、なおかつ自分とお金との感覚を取り戻すための大切な価値観について改めて考えるキッカケとなった。
もし、この先生の授業を受けていたら「家庭科」という学問の重要さに早い段階で気づくことが出来たのは間違いない。だから今後「あの時もっと勉強しとけば良かった」という話題が出た時には自分は最速で「家庭科」と答えることにして、相手にも「家庭科」はいかがかね?と言ってこの本を薦めたい。
参考1)本書の中で述べられている1970年代に流行った「電通の戦略十訓」
ヴァンス・パッカード『浪費をつくり出す人々』がネタ元
1、もっと使わせろ
2、捨てさせろ
3、無駄遣いをさせろ
4、季節を忘れさせろ
5、贈り物をさせろ
6、組合せで買わせろ
7、きっかけを投じろ
8、流行遅れにさせろ
9、気安く買わせろ
10.混乱を作り出せ
参考2)この本で著者によって提出された「反戦略十訓」(購入者目線)
①買いものは必要最小限で済ませよう
②買ったものは、出来る限り使い続けよう
③要らないものは買わないでおこう
④季節に合わせた生活をしよう
⑤贈り物をやめよう(欲しくないものをやりとりしてるだけかも)
⑥単品で買おう(抱き合わせで要らないものまで買わされているかも)
⑦調子に乗せられないようにしよう
⑧流行に乗りたいか考えよう
⑨買う前によく考えよう
⑩落ち着け!本当に必要なものか確かめよう
今回のアイキャッチ画像は以下のサイトより引用。 Designed by Freepik
【関連記事】
関連記事
-
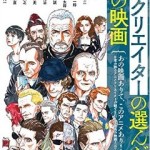
-
【書評】映画秘宝とオトナアニメの究極タッグがついに聞き出した!『アニメクリエイタ―の選んだ至高の映画』(洋泉社)
アニメクリエイターが映画について語る語る 複数のアニメクリエイターが映画について …
-
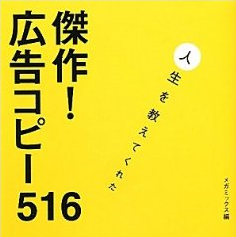
-
傑作の影にクソもあり、メガミックス編『傑作!広告コピー516』(文春文庫)書評
「需要が違うんだから」と女性に言い放つクソ男の台詞とその的外れなダサい広告のせい …
-
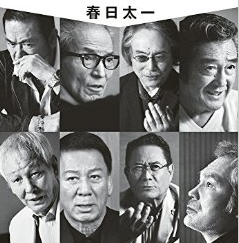
-
生きて語り伝える、春日太一の書籍と最新作『役者は一日にしてならず』(小学館)について
点と点が線になる快感 ドラマも邦画もあまり見てこなかったせいで俳優の名前と顔を一 …
-
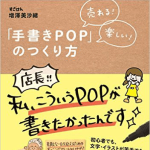
-
画力がレベル1でも関係ねえ!!『売れる!楽しい!「手書きPOP」のつくり方』に感激
POPがこんなに楽しいなんて!!と読んでいるだけで楽しく、実際に「作ってみる」と …
-
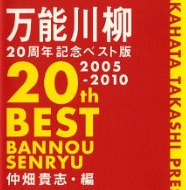
-
264万句のつぶやき、仲畑 貴志『万能川柳20周年記念ベスト版』(毎日新聞社)書評
少し前に広告コピーをまとめた本について書いた時に悪口をたくさん言った。でもその本 …
-
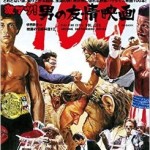
-
【書評】読んで燃えろ、見て燃えろ『激アツ!男の友情映画100』(洋泉社・映画秘宝EX)
【友人として、相手を思い、また裏切らぬ真心】とは「新明解国語事典第6版」に記載さ …
-
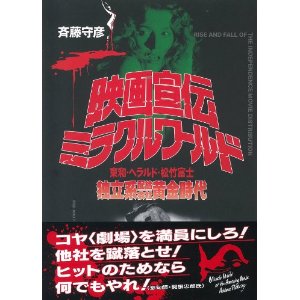
-
【未掲載書評】斉藤守彦著『映画宣伝ミラクルワールド』(洋泉社)~観客に魔術をかけた者たち~
お前のは書評じゃなくてレジュメだと言われて、確かに詰め込みすぎ感はあるということ …
-
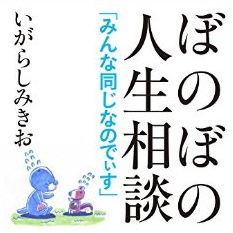
-
「ぼのぼの達と一緒に悩んで考える」いがらしみきお『ぼのぼの人生相談』(竹書房)書評
シマリスくん「(悲しみに)慣れるためになにかした?」 シロウサギくん「してないよ …
-
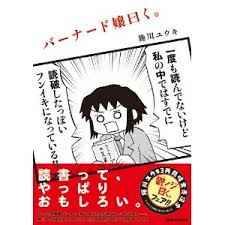
-
名言も豊富!大笑い読書漫画、『バーナード嬢曰く。』感想
本についての漫画や小説は面白い。物語形式でその本についての思い入れを語ってくれる …
-
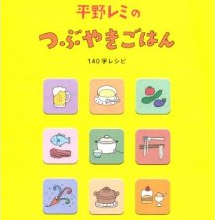
-
料理は名前だ!『「平野レミ」のつぶやきごはん』(宝島社)書評
料理研究家・平野レミがゲスト回の「ゴロウ×デラックス」(2015年2月12日放送 …


