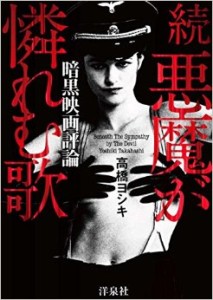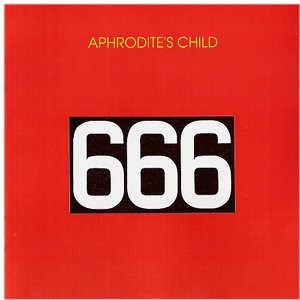【書評】闇があなたを見ている『続悪魔が憐れむ歌』(高橋ヨシキ著、洋泉社刊)
2015/11/27
光と闇に分けられない曖昧な部分が描かれた映画、そこに目を向けるという点でこの続編は前作『悪魔が憐れむ歌』と同じ態度の本ではある。しかしいくつかの論評には現状への強い危機感が含まれているということを切実に感じた。
それはちょっと後半に書くとして、
相変わらず豊富な資料調査やインタビューによって、遠く隔たった歴史的作品の文脈を埋めてくれるので「こういう風に見ることが出来るのか」と驚くことが多い。
はじまりのパワー
ショーン・S・カニンガム監督『13日の金曜日』も、TOKYO MXの放送でもう何度紹介されたかわからないサム・ライミ『死霊のはらわた』も、何故それらの亜流が繰り返し作られ後続の作家はオマージュを捧げるのか。人をそういう欲望に駆りたてる圧倒的な力を持つ「モンスター」、その産みの親たちが当時どのような思想を持って作品を作っていたのかが高橋ヨシキの手によって改めて召喚される。
ジェイソンの衝撃を最大限にするため、作り手はショックの前段階でどうやって観客を安心させたか。色彩学で赤と緑の組み合わせが最悪と言うことで作られたフレディ・クルーガー、彼の見せた「悪夢」はどのような形で視覚的に表現されたか。
定型の物語を少しひねった脚本が横行しているなかそのアイデアで満足している人は(それは自分を大いに含む)亜流の元祖がどれだけ作品として練られ、巨大なエネルギー量を持っていたかについて立ち止まって色々考えるべきなのだ。これはおそらくあらゆる分野に言えるが、この「はじまりのパワー」を受け止めた後に物語をズラすなり反逆していかねばならない。この本は改めてそういうことを考えるキッカケとなった。
前著との違い
さて冒頭の感想にもどる。前作を読んでいる人が本書の後半あたりまでページをめくったとき、文章の調子が少し変わっていることに気づくと思う。
その始まりは「ハルマゲドンがやってくる!」という特集からだ。
「世界が終わる」という黙示録のフィクションがいかにアメリカ映画の中で繰り返し語られているかという記事は実に勉強になる、と同時に「怖い」。
自分たちの言っていることが正しく、最後の審判の日には「我々」が救われ、我々を批判する奴らは地上に取り残され破滅していくという「レフト・ビハインド」の思想。それはドキュメンタリー映画『ジーザス・キャンプ』で語られているように現実の意思決定にも大きな影響を与えている「物語」である。
ここではキリスト教の黙示録のみに焦点が当てられているが、自分たちが正しく他人が間違っているという破滅と救済が一体となった思想は突き詰めると様々な思想に接近していく。
「フィクション」という厄介な問題
人は容易くフィクションに導かれ自らにとって都合の良いものを選び取ってしまう。そうした目線で再解釈されるのがテリー・ギリアム監督の映画『未来世紀ブラジル』である。
この「さらば『未来世紀ブラジル』」という評論がコロンブスの卵のようにこの映画に関しての認識を一変させる。「そうだよ、確かに」と。
主人公サムが官僚社会の歪さに直面する悲劇。著者も従来そうした解釈を取っていたこの作品だが(当然自分も)しかし冷静に主人公のした行為だけを見ていくならば、ヒーローとなって囚われの姫を救い出す妄想をしていた男がその姫によく似た女性があらわれたとき、ブルジョワの小さな権力を用いて彼女を自分のものにする嫌な物語ともいえるのだ。
つまり、この映画は官僚社会の非人間性に対して反抗する話ではなく、ただ幻想に浸り幼稚な逃避をする男の姿を描いているのではないかと著者は認識を改める(そう考えると『エンジェル・ウォーズ』がこの作品に近いというのは違う。あの映画は幻想を使ってどうしようもない現実と戦う映画だったはずだ)
いま、この時代を感じる文章
無数に映画を見てこの現実をやり過ごすこと、それによってこの現実を見ないふりをする男の姿。それは完全に自分にも突き刺さるテーマだ。
現実と戦うためではなく逃げるためにフィクションを用い、肥大化していった自意識の行きつく先が「ナチス」であり、その物語は見るものの望み通りのフィクションを提供する危険な装置なのではないかと著者は問いかける。
そして逃避がさらに「もう起きてしまった現実」への諦念という闇に入り込むと『アクト・オブ・キリング』のあの加害者が撮ったつまらない虚無の映像へと至る。人間はどこまでも残酷になれ(成れ、慣れ)るという著者があらゆる媒体で繰り返し語っている人間の闇に。
フィクションとは何か、魂の「自由」を守る、それが一つの答えであり同時に実に危うい綱渡りだということをこの本は読む人に突きつける。現実を見ろ、そういうことではおそらくない。フィクションのそうした危険性を常に確認しておくことこそ重要なのだと自分はこの本から受け取った。
何やら「おかしな物語」を敷衍させることでほかの物語を許さない態度が跋扈している現状を悪魔主義者だからこそ敏感に嗅ぎつける。だから、ここに収められている文章に自分は同時代性を強く感じたのだ。
今の社会に何かしらの違和感を持っている人は必読の映画評である。
最後に(ラジオから引用)
高橋ヨシキ「僕ねスタートレックというのは、アメリカの良心であると思っているところがあって、人類の未来に対して明るい展望を見せてるんですね。で、人間というのはより良くなれるはずだという根底がたぶんあって」
宇多丸「全然違う人種、違う星の星人、風習があっても・・・」
高橋ヨシキ「そう、それでも最終的に対話は成り立つはずだみたいなことをやってて、面白いのはスタートレックって前のシリーズで敵だったやつが次のシリーズで同盟になってたりするんですよ」
宇多丸「クリンゴンとかね」
高橋ヨシキ「ボーグとか、究極の敵いますけど別のシリーズで手を組んでたり。そういうの含めて楽観主義ていうかね。人種差別にも最初の頃から凄い敏感で黒人女性がメインのクルーにいるなんて番組はそれまでなかった、東洋人もね。そういうのがあるうちはアメリカ人は馬鹿だキチ○イだと言ってもだいたい大丈夫だろうなと思ってました」
宇多丸×高橋ヨシキ「映画が残酷・野蛮で何が悪い」特集より(TBSラジオ「ライムスター宇多丸のウイークエンドシャッフル」2013年8月6日放送分)
【関連記事】
関連記事
-
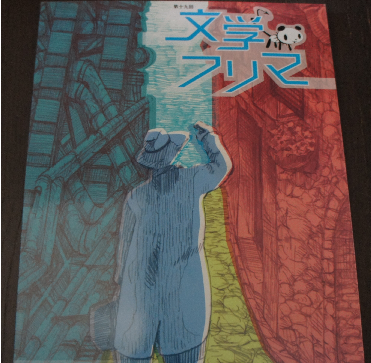
-
「第十九回文学フリマ」へ行って買ってつらつら思ったこと
11月24日(祝)に行われた「第十九回文学フリマ」に行ってきました。前回行ったの …
-
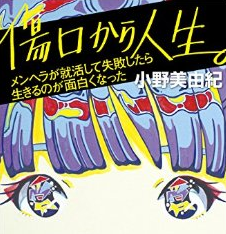
-
武器を理解せよ傷を理解せよ、小野美由紀著『傷口から人生』(幻冬舎文庫)書評
本の正式名称は『傷口から人生。メンヘラが就活して失敗したら生きるのが面白くなった …
-

-
新作STARWARSに備えるためには河原一久のスター・ウォーズ本が良いぞ
2015年はスター・ウォーズの新作が公開されるということもあって世界中で盛り上が …
-
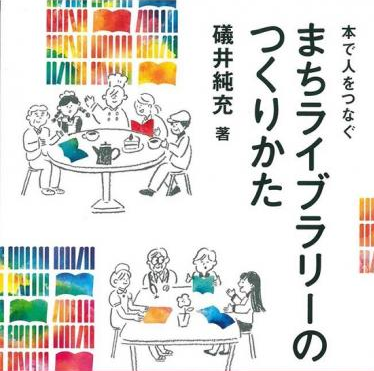
-
本を開きて人が来る、磯井純充『本で人をつなぐ まちライブラリーのつくりかた』(学芸出版社)書評
中学生の頃『耳をすませば』に憧れ、蔵書が凄い図書室を持つ高校(自分にとっては非 …
-
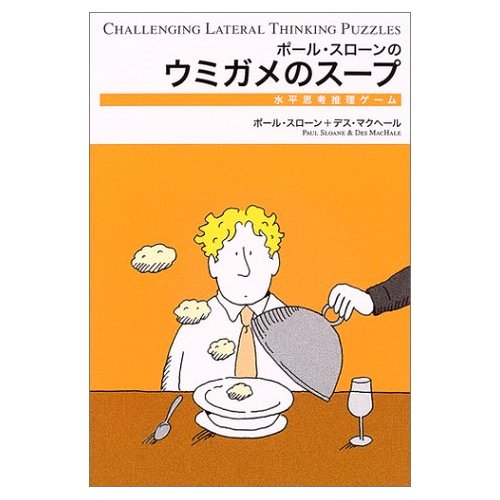
-
~悪問に負けず頭を動かそう~『ポール・スローンのウミガメのスープ』(エクスナレッジ)書評
また2ちゃんねるのオカルト板に入り浸ってしまっていてこんな時間。 東京郊外で心が …
-
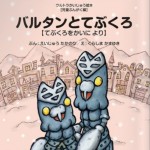
-
名作+怪獣+ウルトラマン=「ウルトラかいじゅう絵本」のカオスな物語たち
ウルトラマン×絵本といえば思い出すのは、子育てに奮闘するウルトラマンやバルタン星 …
-
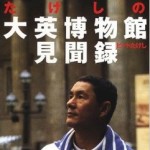
-
【書評】ビートたけしVS大英博物館『たけしの大英博物館見聞録』(新潮社・とんぼの本)
現在、東京都美術館で「大英博物館展―100のモノが語る世界の歴史」が開かれている …
-
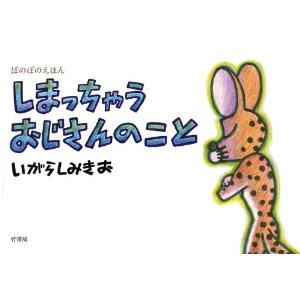
-
知ってる人は知っている名作「ぼのぼの絵本」
「2015年はぼのぼのが熱い」と言う記事を書いてそれなりにアクセスがあるみたい …
-
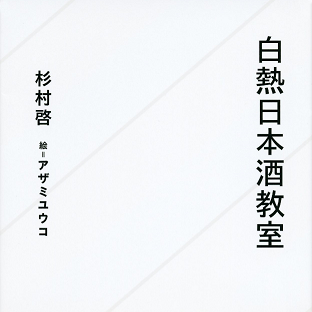
-
買う、読む、飲む。杉村啓『白熱日本酒教室』(星海社新書)書評
「わかりやすさトップクラス」 ・星海社新書の本は導入がうまく、教 …
-

-
嗚呼、ややこしきハラールよ『ハラールマーケット最前線』(佐々木良昭)書評
(内容が厄介なだけに長文です。すまん) Contents1 バンコクで出会った「 …