pha著『ニートの歩き方』(技術評論社)評~走らない生き方~
2015/12/02
前回の記事『無業社会』の書評で働いてないことへの抑圧を軽減することも重要である。と書いた。
どういうことか、もう少し詳しく書くとマクロな視点で「無業社会」をどうにかしていくことを考えるのと共に、個人が自身で「無業状態」の心理的負担を軽減していくのも大事なのだ。
つまり、平日の昼間から若い者がプラプラしていることへの罪悪感を自らの手で少しでも軽くするということでもある。
人生における様々なライフイベントを達成していかないと、お金も場所もなくなり、そのうちに人間関係も無くなっていくという喪失の悲しさを『無業社会』は様々な事例とともに書いていた。そこにあるのは良い人だからこそ、自分が悪いと責め自分を否定してしまう心のありようだ。
処方箋の一つとして有効なのはどうもうまくいかない自分をある種、自明のこととして捉え、「仕方ない」というのをネガティブな意味ではなく現状を認める上で使うことだと思う。
pha著『ニートの歩き方』はそれを考えるうえで格好の本だ。なにせ本書は、
「だるい」「めんどうくさい」「働きたくない」という三語で始まるから。
「だるい」「めんどうくさい」「働きたくない」
この三語への反応としては、
- 本当にそうだよ!!(肯定)
- そうだね(曖昧な笑み、時には失笑)
- 怠けるな!
と大体こんな感じに分かれると思う。
こういうだるい若者、包摂を薦められるが、どうもそこからすり抜けてしまう自分のような若者もやはり存在することを認識したうえで、別に薦めてるわけじゃなく一つの提案=モデルを提供しているのが本書だ。
そしてこの本は非常に良心的だ。
なぜなら5ページ目でいきなりこう述べられている。
「色んなことをあきらめなきゃいけない」
手に入るものではなく失うものから先に書くこと、海外旅行をしたり、車を買ったり、結婚をしたりとそういうことは難しくなるのをちゃんと書いている。
その良心的な書き方は、だからこそ本書の後半での「ニートにも向上心は必要だということ」という文章と繋がる。
怠けているという意見を受け入れながら、しかし向上心とは?
この向上心はお金を稼ぐとかそういうことではなく、少し先の目標を自分で設定しそれに向かって動くということ。おそらく、ここからは自分の意見だが、たとえば美味しいものを食べたいと思った時に、お金を出して美味しいものを買うのではなくて自分でどれだけ美味しいものを作れるか等そういう観点なのだと思う。
世間一般の価値観ではなく自分なりの判断を持つこと、ここでの向上心とはおそらくそういうことだ。
具体例をキチンと書いてある誠実さ
本書の良心的な点はもう一つあって、いますぐの処方箋として様々な具体例がキチンと書いてあるということだ。
そういうところが吐き気を覚えるような抽象的なビジネス書(そのくせ結論は経験に基づく「がんばりなさい!」)よりもはるかに信頼できる。
せどり、プログラミング、ペイパルなどで口座を作りカンパを募る、雇用保険、職業訓練について、実家は死守しろというアドバイスに、ニートのためのブックガイド・・・etc
普通に働けば、と笑う人もいるかもしれない、しかし小銭稼ぎに過ぎないこれらのことが実践的で切実な答えなのだ。そして何をしていいか途方に暮れているときに指標となる。笑わないし、笑えない、今はもうそういう時代でもある。そういう時代の人々のためのブックガイドだ。
若干の留保をするなら、著者は28歳で仕事を辞めた時に貯金が300万円あり、京都大学を卒業していること。この本で書かれてる実践は地方では難しいのではないかということ。せどりは既に儲からないということなどがある。
そういった疑問や注意点もあるが、実際そこはどうでもいい。その批判は「○○だから上手くいってるんでしょう」ということにしか繋がらない。重要なのはこの本の具体例の提示によって心理的な負担が軽減されることだ。実践方法も教えることで読者はそれをアレンジする機会にも結び付く。
だから、もし何らかの拍子に自分の中で何か駄目になっていく感覚を覚えたのならニートになるつもりはなくてもこの本を紐解いてみるといいかもしれない。
何のために?金になる?など関係なく、楽しいからやるという感覚に少しの勇気をもらえるだろう。『無業社会』とは違うが、これもまたシステムを見つめたうえでどういう生き方を選ぶかの参考となる包摂の本なのだ。
最後に、本書の中で一番好きだった言葉の引用。
働かずに食うめしはうまいか
働いても働かなくても飯はうまい。
著者のブログ「phaのニート日記」 phaの日記
【関連記事】
- 「ぼのぼの達と一緒に悩んで考える」いがらしみきお『ぼのぼの人生相談』(竹書房)書評
- ビジネス書中毒に注意せよ!『読書で賢く生きる。』(ベスト新書)感想
- 【書評】『教養は「事典」で磨け』(光文社新書・成毛眞)&おすすめの事典三冊
関連記事
-
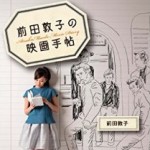
-
【書評】初々しい言葉の連なり『前田敦子の映画手帳』(前田敦子・朝日新聞出版)
映画を見ないとその日は落ち着かないくらい、いま映画にはまっています。一日に何本も …
-
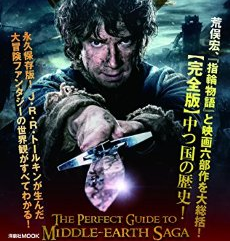
-
いまふたたびの中つ国へ、別冊映画秘宝『中つ国サーガ読本』書評
ビルボ・バギンズ(マーティン・フリーマン)の格好良すぎる表紙に書店で引き寄せられ …
-
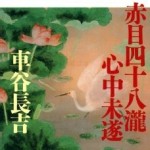
-
【私的印象批評】底を求める/書くことの業『赤目四十八瀧心中未遂』(車谷長吉、文春文庫)
車谷長吉の直木賞受賞作『赤目四十八瀧心中未遂』は、主人公である「私」が数年前に地 …
-
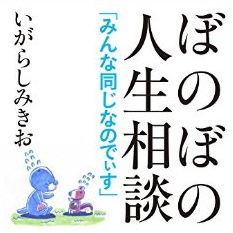
-
「ぼのぼの達と一緒に悩んで考える」いがらしみきお『ぼのぼの人生相談』(竹書房)書評
シマリスくん「(悲しみに)慣れるためになにかした?」 シロウサギくん「してないよ …
-

-
【書評】青ペン効果。信じるか信じないかは・・・『頭がよくなる 青ペン書きなぐり勉強法』(相川 秀希・KADOKAWA/中経出版)
『頭がよくなる 青ペン書きなぐり勉強法』(相川 秀希・KADOKAWA/中経出版 …
-

-
反スペクタクルへの意志『テロルと映画』(四方田犬彦・中公新書)感想
映画は見世物である。激しい音や目の前に広がる大きなスクリーンによって人々の欲望を …
-
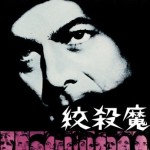
-
血とおっぱいに祝福を『トラウマ日曜洋画劇場』(皿井垂・彩図社)書評
かつてテレビで毎日のように映画を流していた時代があった。 ・・・と、ちょっと前に …
-

-
女性器サラリと言えますか?『私の体がワイセツ?!女のそこだけなぜタブー』(ろくでなし子、筑摩書房)感想
検索結果の順位が下がったり、サイト全体の評価が下がったりとそういうことで、グーグ …
-
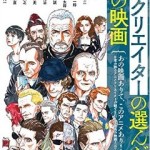
-
【書評】映画秘宝とオトナアニメの究極タッグがついに聞き出した!『アニメクリエイタ―の選んだ至高の映画』(洋泉社)
アニメクリエイターが映画について語る語る 複数のアニメクリエイターが映画について …
-

-
嗚呼、ややこしきハラールよ『ハラールマーケット最前線』(佐々木良昭)書評
(内容が厄介なだけに長文です。すまん) Contents1 バンコクで出会った「 …


