血とおっぱいに祝福を『トラウマ日曜洋画劇場』(皿井垂・彩図社)書評
2015/11/27
かつてテレビで毎日のように映画を流していた時代があった。
・・・と、ちょっと前にこんな感じで始まる「テレビと映画」についての記事を書こうとしたことがあった。しかし、そういや俺「木曜洋画劇場」しかちゃんとした知識の元がない・・・という絶望的知識の浅さに途中で書くのをやめたのだった。
昨日、彩図社から刊行されている『トラウマ日曜洋画劇場』(皿井垂)を読み終わり、実際どんな悪魔的な映画が流されていたのか、その実情の一端に改めて触れることが出来た。
- 「日曜洋画劇場」での『地獄に堕ちた勇者ども』(監督:ルキノ・ヴィスコンティ)
- 「月曜ロードショー」での『ときめきに死す』(監督:森田芳光)
- 「水曜ロードショー」での『カサンドラ・クロス』(監督:ブライアン・デ・パルマ)
- 「ゴールデン洋画劇場」での『青い体験』(監督:サルヴァトーレ・サンペリ)
- 「木曜洋画劇場」での『絞殺魔』(監督:リチャード・フライシャー)
まずその時代に生きていない自分としては、今では信じられない類の質の高い映画が地上波で放送されていたことに読んでいて衝撃を受ける。どれも幼少期・思春期に見たら確実に「ダメージ」を喰らうのは間違いない、本のタイトルに「トラウマ」と付けられる理由もわかるというもの。ここに羅列されている作品は「印」のようにある年代以上の映画ファンの心に刻みつけられているということだ。
羨ましすぎて仕方ない感情と共に、しかし拙いながらも自分で記事を作る身としてはこの本の体裁や書き方は練度が弱く感じられた。
当時を知る人にとっては、あらすじの羅列でもその人自身の記憶が呼び起こされるから良い。けれどそれ以外の人にはやはり筋の書き方が冗長。脚注にしても「地獄の黙示録」の作品概要について書かれていたりはするのに、チッチョリーナ(イタリアのポルノ女優で政治家)などの時代を反映した固有名詞については省かれており基準がわかりづらい。つまり、どういう読者へ届けたいのかがはっきりしない。
「テレビにおける映画」を書くならば、映画の筋を述べるだけではなく吹替や削除箇所、解説者や同時間帯の番組、作品リストなど様々な方向性があると思うので、そういう側面や「テレビ」というメディアについての考察、その世代を知らない自分が学べるような文脈を補強してくれる深い解説が欲しかった。
個人的には『青い体験』における著者の一秒でもおっぱいが映っていたら正義と捉える主観に満ちた文章が好きだ。個人的なエピソードでありつつ、テレビに付随する「家庭」という場から生じる親の目を逃れ「おっぱい」とどのように謁見すべきかという認識は、木曜洋画劇場で放送された『キリング・ミー・ソフトリー』のソフトSM場面をいかに権力の目をかいくぐり見ることに成功したかという自分の苦闘と重なり、世代を超えて著者と握手できた。
今はそういう時代ではない。思えば遠くきたもので、「アベンジャーズ」は吹替とCMでずたずたにされる現状、赤い血もおっぱいも満足に見ることが出来ないなめられた世界である。もちろん、そういう世界でもメディアの内部にいて映画解説を続けるライムスター宇多丸、高橋ヨシキや町山智浩といった存在がいる。その同時代性に感謝しつつ、ノスタルジーだとわかっていても本書は羨ましさと寂しさを喚起させる。
かつてテレビで毎日のように映画を流していた時代があった。
↓テレビで流してた映画について知りたいならこの本もおすすめ。
【関連記事】
関連記事
-

-
人に映画を薦める作法を『ブラマヨとゆかいな仲間たち アツアツっ!』ライムスター宇多丸ゲスト回から学ぶ
2013年6月22日放送『ブラマヨとゆかいな仲間たち アツアツっ!』のライムスタ …
-
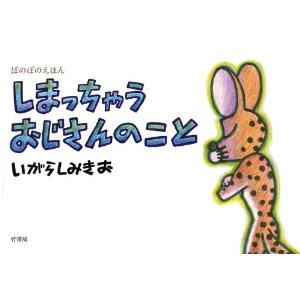
-
知ってる人は知っている名作「ぼのぼの絵本」
「2015年はぼのぼのが熱い」と言う記事を書いてそれなりにアクセスがあるみたい …
-
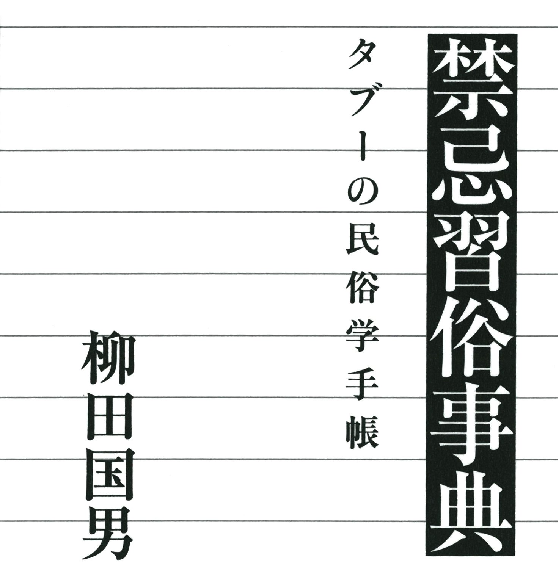
-
~禁忌への想像力~柳田国男『禁忌習俗事典 タブーの民俗学手帳』(河出書房新社)評
タイトルにつられて購入。「禁忌」と聞いて右目が疼く。 しかし事前に想像していたそ …
-

-
はに丸の鬼畜ジャーナリズム「はに丸ジャーナル」(NHK)が熱い
黄金週間なのに黄金がないので、ゴロゴロと居間で寝転んでいたら・・・ はに丸「討論 …
-
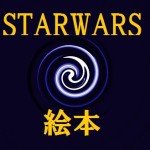
-
スターウォーズ最新作の前にスターウォーズ絵本で優しい気持ちに包まれる
引き続き、12月のスターウォーズ最新作に備えて旧作の見直しと関連書籍を読みふけっ …
-
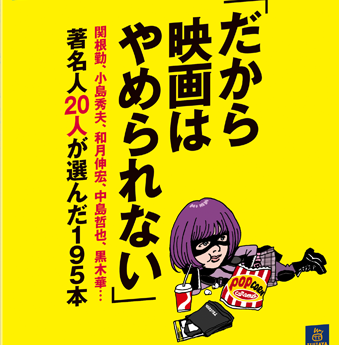
-
200円で買える「TSUTAYAシネマハンドブック」が今年も相変わらずの凄さ
(順次更新) 毎年年末になるとTSUTAYA店頭で並べられる「TSUTAYAシネ …
-
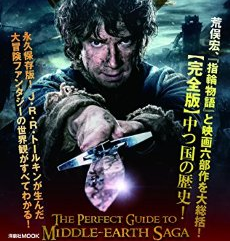
-
いまふたたびの中つ国へ、別冊映画秘宝『中つ国サーガ読本』書評
ビルボ・バギンズ(マーティン・フリーマン)の格好良すぎる表紙に書店で引き寄せられ …
-
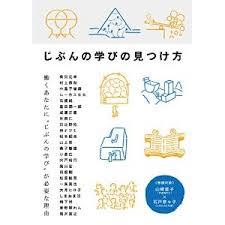
-
~学びの達人たちの事例集~フィルムアート社『じぶんの学びの見つけ方』評
この本の刊行記念トークショー(←詳細はこちらから見れます)にこの本を読まずに行っ …
-

-
日本酒の本を選ぶなら「はせがわ酒店」監修の『日本酒事典』を読もう!
このあいだの山同敦子『めざせ!日本酒の達人』(ちくま新書)の評で自分が何を言って …
-
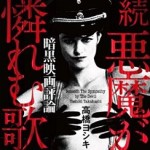
-
【書評】闇があなたを見ている『続悪魔が憐れむ歌』(高橋ヨシキ著、洋泉社刊)
光と闇に分けられない曖昧な部分が描かれた映画、そこに目を向けるという点でこの続編 …


