~禁忌への想像力~柳田国男『禁忌習俗事典 タブーの民俗学手帳』(河出書房新社)評
2015/12/02
タイトルにつられて購入。「禁忌」と聞いて右目が疼く。
しかし事前に想像していたそういうのとは全く違った。当たり前だよね柳田国男の本だし
「我邦では現在イミという一語が、かなり差別の著しい二つ以上の用途に働いている。(中略)忌(イミ)を厳守する者の法則にも、外から憚って近づかぬものと、内に在って警戒して、すべての忌で無いものを排除せんとする場合がある。かように両端に立ち分れているものだったら、最初ひとつの語によってこれを処理しようとするわけがない。」序文より
ちょっと呑み込みづらいけど。つまりこういうことかと思う。「忌(イミ)」には祭りの火のような外から中心への清浄なものへの指向性(しかし近づいてはならない)と、身内に不幸が出た場合などの事例にあるような家の「中」にいつつ外のものを排除する両方の側面がある。現在それは相反するものと思われているが、しかしそれは何かの精神性によって一語のうちに以前は重なっていのだったのではないかという柳田の問題意識をここで述べているのだ。(たぶん)
「以前は今より感覚が相近く、かつその間にもっと筋道の立った脈絡があったのではあるまいか」(本書p3)
ということで色んな田舎の「禁忌」に関する用語を集めたのが本書ということになる。差別と穢れを考察する上での重要な資料として、しかし元の著作を『禁忌習俗語彙』と題されていたこの本は「柳田国男全集」には未収録だったらしい。2014年にめでたくこのような形で復刊、万歳。
東京郊外生れ、東京郊外育ち、民俗学の著作を読んだことがないし、柳田の本も『遠野物語』をチラ見した程度の私、柳田に関しても学術的には様々な批判が既にあると思うが、そういうバックグラウンド関係なくこの本めちゃくちゃ面白かった。最初の序文は難しいけど後はもう楽。読者としては心のおもむくままわからないのは飛ばして読めばいい。
例えばこんなのが出てくる
踏合わせ(フミアワセ):出産、死亡または自害人などのある処、或いは忌中の家に、行き合せた者にはこの穢がある。古い記憶にはこれを触穢と言っている。
これはわかると思う。こういう思想から葬式の後には今でも塩を撒くとかを行うし。
ではこういうのはどうだろうか。
ゲタイ:祭礼に舞人が何か故障を生じて、最後まで勤め終えぬことをゲタイを起すといい行が足りないからだと考えられている(鹿角)
そしてこういうのになるともう論理が謎で面白い。
鉢割れ(ハチワレ):犬猫の斑毛が顔の真ん中で左右に分れ、鼻筋の白く通ったのを鉢割れと言って忌むことは、関東も近畿も一様であり、山で働く人は殊にこの鉢割れの犬を嫌う。壱岐ではそういう猫を「ヒテワレネコ」と言い、主人を見捨てるといって家に飼うことを嫌う。
用語は「忌の状態」「忌を守る法」などと題された目次に配置されているけれど、そのなかでも特に面白いのが「忌の害」「物の忌」の項。上記の項目はなかなか笑える用語、けどここにくると背筋がゾクッとするような暗い精神性を漂わせたものもあったりして、しかもそれについての詳しい説明はないものだから下手なホラー小説よりよっぽど怖い。
袋子(フクロゴ):妊婦は糠袋・茶袋・枕等の袋物を縫ってはならぬ。そんなことをすると袋子を産むという(泉北)
首切石(クビキリイシ):伊勢の三重郡では、縞の入った石を首切石というのは形から思いついた名のように思われるが、これを拾うと首を切られるという。知らずに拾ったらそっと首を三度撫でてから捨てよともいう。(郷土石号)
今は使われない言葉が何か別の論理で動いていること。そうした感覚を想像するのは何か訴えかけてくるものがある。失われた用語(そして少しは繋がっている用語)への想像力と言うことで、こことは違う論理で物語を作りたい、またつなげたいという創作者にとって様々なイメージが浮かんでくること必須の書。必ずや有益なり。
【関連記事】
関連記事
-
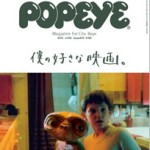
-
雑誌『POPEYE6月号』「僕の好きな映画」特集は時に面白く、たまにむかつく
男「ETってやっぱ面白いよね」 女「わかる。あたしなんてあのテーマ聞いただけでう …
-
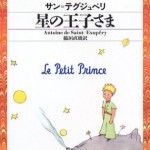
-
映画『リトルプリンス星の王子さまと私』を見る前に再読しませんか原作
2015年11月21日に公開される映画『リトルプリンス星の王子さまと私』は、とあ …
-

-
【書評】青ペン効果。信じるか信じないかは・・・『頭がよくなる 青ペン書きなぐり勉強法』(相川 秀希・KADOKAWA/中経出版)
『頭がよくなる 青ペン書きなぐり勉強法』(相川 秀希・KADOKAWA/中経出版 …
-
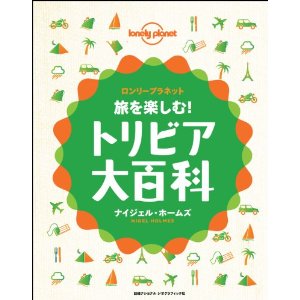
-
旅を本当に楽しむための本『旅を楽しむ!トリビア大百科』
一時期、「1秒間」に世界ではどんな出来事が起きているかという広告が電車内に掲載さ …
-
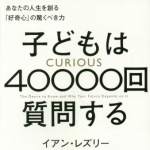
-
子どもが常に好奇心を持っているなんて大間違い!『子どもは40000回質問する』(イアン・レズリー/光文社)感想
40000回、これは2歳から5歳までに子供が説明を求める質問の平均回数だという。 …
-
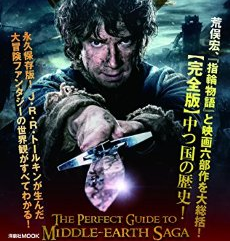
-
いまふたたびの中つ国へ、別冊映画秘宝『中つ国サーガ読本』書評
ビルボ・バギンズ(マーティン・フリーマン)の格好良すぎる表紙に書店で引き寄せられ …
-
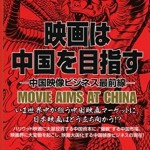
-
【書評】『映画は中国を目指す』(洋泉社・中根研一)
「アイアンマン3」「ダークナイトライジング」「パシフィック・リム」・・・近年のハ …
-
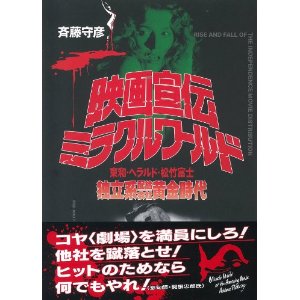
-
【未掲載書評】斉藤守彦著『映画宣伝ミラクルワールド』(洋泉社)~観客に魔術をかけた者たち~
お前のは書評じゃなくてレジュメだと言われて、確かに詰め込みすぎ感はあるということ …
-
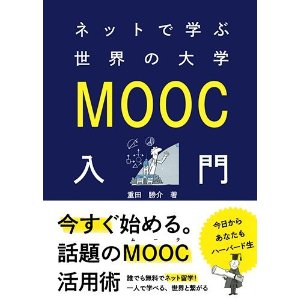
-
~これからは家で留学の時代!?~重田勝介著『ネットで学ぶ世界の大学MOOC入門』(実業之日本社)評
「あなたはMOOC(ムーク)を知っているだろうか?」 …
-
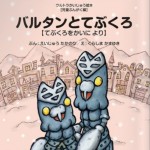
-
名作+怪獣+ウルトラマン=「ウルトラかいじゅう絵本」のカオスな物語たち
ウルトラマン×絵本といえば思い出すのは、子育てに奮闘するウルトラマンやバルタン星 …

