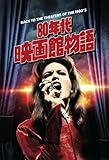【未掲載書評】斉藤守彦著『映画宣伝ミラクルワールド』(洋泉社)~観客に魔術をかけた者たち~
2015/12/02
お前のは書評じゃなくてレジュメだと言われて、確かに詰め込みすぎ感はあるということで以前書いた斉藤守彦著『映画宣伝ミラクルワールド』(洋泉社)の文章の元となった800字書評を掲載します。
何故このタイミングかというと、別に出した書評の方が掲載されることになったのと、もっと多くの人にこの「熱い」本を読んでほしいのと著者の新作『80年代映画館物語』が12月4日に発売になったから。
「1980年代、東京では世界中の映画を見ることができた! シネコンが台頭する以前、映画館が最もラジカルだった時代、そこで何が起こっていたのか? 」(公式サイトより)
なおかつ「1980~1989年に上映された都内主要映画館番組表 」が凄い力作でその作業を考えると震えた。
ある時期の映画について異様に詳しく話す人がいる。
熱っぽく話すその人に次々と同じ熱を持った人が集まる。
こういう場面に何度も遭遇した。話を聞いていると断片としてその映画の知識は入ってくる。しかし何が彼らをここまで突き動かしているのか、それがわからなかった。
この本を読んでその疑問は解決した。彼らが話していたのはすべて1970年代後半から1980年代の洋画だった。それもメジャー系の配給ではなく、買付・営業・宣伝まで自社の判断で動ける「独立配給系」の映画である。
本書は、資本の少なさを様々なアイデアでカバーし伝説に残る手法を築き上げた「独立配給会社」の活躍と当時の状況を、関係者へのインタビューを含めユーモアを含めて冷静に、そして時に滲み出る怒りとともに描いている。
そこで語られるエピソードはすさまじい。困ったことにそれが時に映画以上に面白いのだ。例えば、一瞬でも宣伝に使えそうな象徴的なシーン=キラーショットがあったら、それを極限まで展開する「ハッタリ手法」である。映画『サランドラ』では、一瞬だけうつる大柄のナイフを「ジョギリ」と勝手に命名、それで殺人が行われるように宣伝し木製のレプリカナイフを映画館前に設置するという荒業。
そして、そのナイフは映画初日に怒りに満ちた観客に壊された。観客もすさまじい時代だったのだ。
あの手この手で大手に負けずに映画館を満席にしたいという熱い思いは、しかし時代という壁にぶつかる。全国一斉上映の一本立てによる映画のメジャー方向へのシフト、週末にゆったり見る映画としてのレンタル屋の普及。だんだんと「独立配給映画」の熱さが薄れていった寂しさを含ませ本書は終わる・・・いや終わらない。
最後にあっという驚きが読者を待っている。あの世界的な大作映画のキャッチコピーに「独立配給会社」の血が流れていると知ったとき、いまだに熱い記憶は受け継がれていると思い感動を隠せなかった。この本には大文字の映画史には残らない「熱い」現場の映画史が描かれている。
【関連記事】
関連記事
-

-
嗚呼、ややこしきハラールよ『ハラールマーケット最前線』(佐々木良昭)書評
(内容が厄介なだけに長文です。すまん) Contents1 バンコクで出会った「 …
-

-
面白いインド映画を探すならこの本!『インド映画完全ガイド』
踊らない、そして伏線を巧みに利用した洗練されているインド映画が増加中である。 た …
-
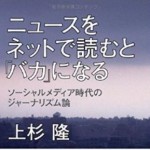
-
【書評】おそるべきめいちょ『ニュースをネットで読むと「バカ」になる ソーシャルメディア時代のジャーナリズム論』(上杉 隆著、KKベストセラーズ刊)
様々な歴史的な経緯を経て、ネットには大手メディアが報じない真実があるというのは嘘 …
-

-
映画館はつらいよ『映画館のつくり方』(映画芸術編集部)
映画好きなら1度は考えるかもしれない。 「映画館を運営するということ」 しかし、 …
-
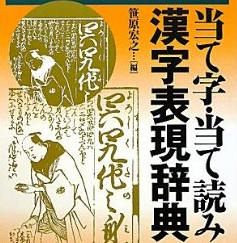
-
運命は「さだめ」な笹原宏之編『当て字・当て読み漢字表現辞典』(三省堂)
今日紹介するのは「妄想型箱舟依存型症候群」と書いて「アーク」と読むサウンド・ホラ …
-
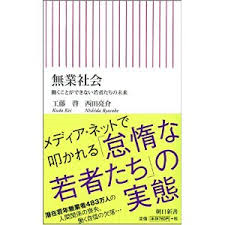
-
工藤啓・西田亮介『無業社会』評~根性論からの脱却~
朝日新書『無業社会』工藤啓・西田亮介(著)を読みながら、他人事じゃないという強い …
-
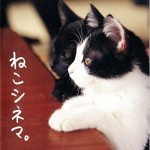
-
『ねこシネマ』を読んでロシア映画『こねこ』を見て悶えて日が暮れて
なにやら猫がブームである。 書店に行けば猫関連の本で棚は埋め尽くされている。自分 …
-
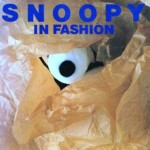
-
スヌーピー95変化!貴重な写真集『スヌーピーインファッション』(リブロポート)
ずっと見たかった『スヌーピーインファッション』をようやく入手。 ええ、たまらなく …
-

-
【書評】家庭科を食らえ!『シアワセなお金の使い方 新しい家庭科勉強法2』(南野忠晴、岩波ジュニア新書)
「ああ学生時代もっと勉強しとけば良かった」 こんな言葉に巷で良く出会う。「どの教 …
-
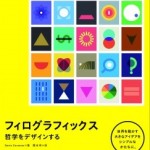
-
【書評】言葉以外を武器として『フィログラフィックス 哲学をデザインする』(ジェニス・カレーラス・フィルムアート社)
フィルムアート社から4月に出版されたジェニス・カレーラス著『フィログラフィックス …