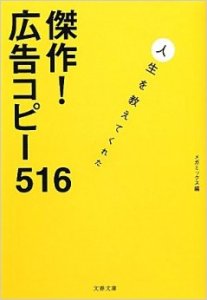傑作の影にクソもあり、メガミックス編『傑作!広告コピー516』(文春文庫)書評
2015/12/02
「需要が違うんだから」と女性に言い放つクソ男の台詞とその的外れなダサい広告のせいで批判が殺到したルミネのCM。
「そういうことじゃねえよ」「作った時に問題だと思わなかったのだろうか」と謝罪文含めて話題になったが、twitterで読んだ感想のひとつに「時代錯誤も甚だしい」というのがあって、最近読んだ『傑作!広告コピー516』という本を思い出した。
この本は80年から2001年に生まれたコピー作品から516本を選んで歌集のように並べたものである。コピーとかは好きだし、文庫で714円+税ということで空いた時間にパラパラと読むのにピッタリで、自分の心に響いたものでも軽くブログの記事にまとめようと思っていた。
が、この本あまりにもセンスがないのである。
広告と言うのは時代を映す鏡である。
だから80年代にひどいコピーがあってもある程度は仕方がない。問題はコピーの一つ一つに、編集者だろうか?それについての感想が掲載されていて、それがまさにあまりにも時代錯誤のトンチンカンな内容なのである。
ということで感想を書くのはやめにしたのだが、ルミネのCM騒動を見ていて、この本の残念なコメントは、むしろ残念な人の思考法を垣間見れて面白い一冊となるのではないかと思い直した。
ということでいくつか紹介。
まずは軽いジャブ。
「私の化粧のことで場が盛り上がってます」
(門田 陽/マツヤレディス、2000年)
この言葉自体はまったく問題ない(と思う)で、この本がいかに残念かとして最初に持ってきたのはこのコメントのためである。
「もしも職場にゴージャス系の女性がいなかったら男性社員のモチベーションは下がるというもの」
凄いでしょ?
こんなコメントがこの本は続くのである。うーむ(笑)別にこの化粧はゴージャスなわけでも男性の話をしている訳でもないと思うのだが・・・。取り上げる気はなかったが、ふと横のページを見たら「メイクをした顔が、自分のほんとうの顔だと思う」(岩崎俊一/西武百貨店スタイリッシュライフカレッジ、2001年)に付記されたコメントも凄い。
「顔がマズいと外にも出られないっしょ。一人前の女として堂々、外出できるのは、メイクのうれしいマジックのおかげです」
何だろうこの上から目線w、全体的に上からなんですけどね・・・。
さて次、
「やっと、男ができました。それで、やさしくなりました」
(吉永淳/流行通信社、1989年)
時代っすなあ・・・そしてコメント。「恋をすると痛みを知ります。痛みを知った人は、心からやさしくなれます。恋は、素晴らしい魔法です」
2000年代に何の疑問もなく、このコピーを素晴らしいと言ってる感覚がほんと頭悪くて素晴らしい。
「いまは女が醜くなれない時代だと思う。でもきっとそれは女にとって幸せなことよ。」
(西村佳也/サントリーオールド、1983年)
これは時代関係なく広告自体があまりよろしくない気もする。さてさて、それについてのコメント「1983年には、こんなコピーが新鮮でした。でも、OLがオヤジ化している今こそ、このコピーの重みを感じるのです。」
いやあ意味がわからないコメントだ、強力!!!
さてラスト!
「もしも、女性に魅力がなかったら、人類は、この先どうなるでしょう。」
(一倉宏/ポーラ化粧品、1992年)
知らんがなの広告に続いて、最大級のひどいコメント
「女性が女を捨てオバサン化したら、男は生きる喜びを失います。それどころか、結婚率、さらには出産率にまで悪影響が生じ、人口減少にまで波及するかもしれません。あなたが魅力的でいるのは、世のためなのです」
・
・
・
取り上げているのが女性に関しての広告だけと思われるかもしれないが、男に関係のあるコピーは男の美学とかが多く、そのほとんどすべてのコメントが自分に酔っていて気持ち悪いだけなのですが、こんなヤバいのもある。
「ぶんなぐられて、男になった」
(魚住勉/小学館・郷ひろみ『たったひとり』、1981年)
コメント
「殴られることの痛みは心の痛み。男は痛みをいっぱい身に受けて、忍耐力や優しさ、包容力を身につけて、より男らしくなっていくのです」
・・・終わりに。
本書で収録しているコピーの中には「ああ時代だなあ」と時代を感じさせるのもある一方で「毎日ビールを飲んだ。それでも渇いていた」(キリンビール)、1989年・伊勢丹の「恋が着せ、愛が脱がせる」、「頭にくるけど、男の視線は足にくるのね」(ドクターショール)←(イラッと上手いの中間ぐらいを攻めてるコピー)などいつまでも人を惹きつける色褪せない言葉も数多く収録されている。
そうした言葉の持つ力が、残念なコメントが付記されることにより増幅する。つまりこの本は素晴らしいものとダサいものが両方一度に味わえる実にお得な本と言うことが出来る。出来ると思う、出来てほしい。そういう意味でお得な一冊となっている。巻末に収録されている歌人・穂村弘の解説はさすがの上手さなのでオススメ。
最後に自分が好きな本書に収録もされている広告コピー。
「20歳までに、僕はいくつ河を渡るだろうか」
(秋山晶/パイオニア/ランナウェイ、1981年)
↑谷山雅計『広告コピーってこう書くんだ!読本』は「広告コピー」ということで思い出した本。この本に書いてある「古本屋にどうやって人を呼び込むか?」を例とした広告コピーの発想話はめちゃくちゃ面白かった。「香り」「温故知新」「涙」「あたたかさ」など駄目な典型例を見事に自分が作ってしまったために、著者の発想には目から鱗が落ちた。
【関連記事】
関連記事
-

-
人は死ぬとき何を詠うか『辞世の歌』(松村雄二・三笠書房コレクション日本歌人選)
体調を崩してからヴァージニア・ウルフやボラーニョ、伊藤計劃の日記などを意識して読 …
-
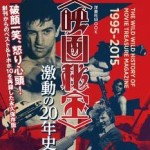
-
This is eigahiho!『<映画秘宝>激動の20年史』 (洋泉社MOOK)感想
タイトルは『300』的なノリで。 現在も大々的に刊行されている映画雑誌といえば『 …
-
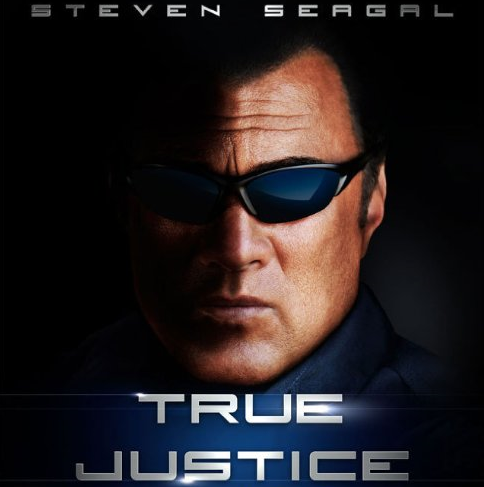
-
「セガール劇場」番組欄に溢れるテレビ東京スタッフのセガール愛
以前に比べて外出の機会が少なくなった結果、体力が落ち近頃は風邪を引くことが多くな …
-

-
【書評】青ペン効果。信じるか信じないかは・・・『頭がよくなる 青ペン書きなぐり勉強法』(相川 秀希・KADOKAWA/中経出版)
『頭がよくなる 青ペン書きなぐり勉強法』(相川 秀希・KADOKAWA/中経出版 …
-

-
~哲学者の苛烈な批判~、ショーペンハウエル『読書について』(コンクール用の下書き)
毎年、光文社では課題本を設け「古典新訳文庫エッセイコンクール」と称し幅広く文章 …
-
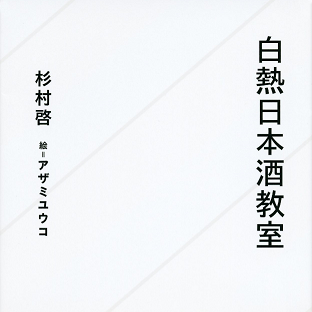
-
買う、読む、飲む。杉村啓『白熱日本酒教室』(星海社新書)書評
「わかりやすさトップクラス」 ・星海社新書の本は導入がうまく、教 …
-
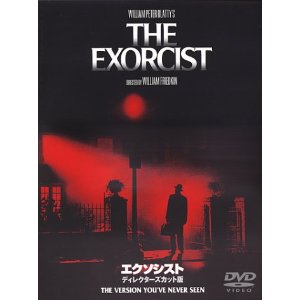
-
「バラいろTHEMOVIE」最終回のトークまとめ
TOKYO MXで午後9時から放送してる『バラいろダンディ』 金曜日の1コーナー …
-
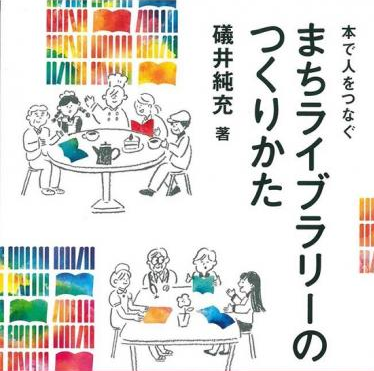
-
本を開きて人が来る、磯井純充『本で人をつなぐ まちライブラリーのつくりかた』(学芸出版社)書評
中学生の頃『耳をすませば』に憧れ、蔵書が凄い図書室を持つ高校(自分にとっては非 …
-
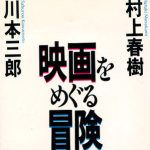
-
村上春樹語る!川本三郎まとめる!貴重な映画本『映画をめぐる冒険』書評
村上春樹の貴重な本といえば若いころに村上龍と対談した『ウォーク・ドント・ラン』が …
-
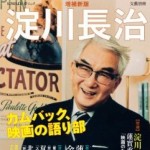
-
映画への畏怖を叩き込まれる名著『淀川長治 —カムバック、映画の語り部』(河出書房新社)感想
最近は映画について書くことに悩んでいて、単体の映画について善し悪しを言うよりも。 …