~哲学者の苛烈な批判~、ショーペンハウエル『読書について』(コンクール用の下書き)
2015/12/02
毎年、光文社では課題本を設け「古典新訳文庫エッセイコンクール」と称し幅広く文章を公募している。
いくつかの部門にわかれるこの賞は、大学生・一般部門もあるので 社会人も参加できるコンペとして毎年かなりの数の文章が投稿される。 そして、このコンペは2000字以上という本格的なもの。さらに大学生・社会人の課題本は
- リルケ『マルテの手記』
- シューペンハウエル『読書について』
- J・S・ミル『自由論』
という癖のある三冊。 しかも論文という形式ではなく一冊の本について読ませる「2000字」の文章というのが思いのほか難しい。
キャッチコピーだったら切れ味、140字だったら印象論と自分なりのひねった意見、400字だったらハッタリと読むべき理由などで読者は結構目に留めてくれるが 800字からは細かな情報をどのように入れるか、「あらすじ」および論の展開をどうするかといった論理力なども必要とされる。
光文社
売り上げランキング: 114764
というわけで今回は、ある程度これらの本の内容について述べることで、この文章単体でも読める提出用原稿の下地を形成したい(希望)
Contents
三冊の中で一番短いショーぺンハウエル『読書について』
・岩波文庫でも出版されている読書論の名著だが、これが本当に厄介な代物。 この本いきなり

「自分の考えを持ちたくなければ、その絶対確実な方法は、一分でも空き時間が出来たら、すぐさま本を手に取ることだ」(p10)
なんてこと書いてやがる。
そう、この本は「読書はあまりしてはいけない!」という反読書法の立場から書かれた読書本なのだ。 しかも、その論証がコンパクトでありながら見事で、語られる比喩も「上手い!」と書きとどめたくなる出来。 そして、正論であるからこそなんだか無性に腹が立つ本である。
いったいここに書かれていることでまったくドキリとしない読書家なんているのだろうか?と何度読んでも思う。 「自分の頭で考える」「著述と文体について」「読書について」の三篇からなるこの本の底に流れている思考は同一である。拙い要約してみる。
反読書と言うが、詳しく述べると「反多読」
「重圧を与え続けると、バネの弾力がなくなるように多読に走ると精神のしなやかさが奪われる」(p10)
読書は思考の泉が枯れたときに栄養源を供給するためのものであり、思索の段階になったときにも関わらず あれやこれやと読んでいると思想が未消化のまま、思索が本に乗っ取られてしまう。 本を手に取って思索から逃げ出すことは、
「広々した大自然から逃げ出して、植物標本に見入ったり、銅版画の美しい風景を眺めたりする人に似ている」(p13)
これは「博覧強記」と呼ばれている人たちによく見られ、彼らと偉大な思想家との違いは 偉大な思想家は体系を持ち、多く読んでも思想が有機的に広がっていく、つまり知識のなかに思想が通奏低音のように響いているが「博覧強記」と呼ばれる人たちは音楽の切れ端を捕まえているにすぎず迷走している。
だから、たとえ自分の頭で考え着いたことがすでに書かれていたとしても、それは自分の中の体系から編み出したもので価値がある。
自分の頭で考えない読書家は文章にも性質が現れる
そして、自分の頭で考えることをしないものたちの読書に関する感覚は書くことについても性質として現れる。(「著述と文体について」の議論) 書くことにはいくつかのパターンがあるが、 「テーマがあるから書く」「書くために書く」 が存在する。
また書き方に関しては ①「考えずに書く」 ②「書きながら考える」 ③「考え抜いて書く」がある。
考えずに書くことは記憶や本の借用に頼って書くことと批判し、書きながら考えることは「運を天に任せて猟に出かけるが、帰路につくのはむずかしい」として揶揄している。 つまりショーペンハウエルが理想としているのは
テーマがあるから書き、それは最初から最後まで帰路までの道を含め考え抜いていなければならない。
ということだ この辺から、だんだんとショーペンハウエルの語調が荒くなるのも面白い。 金のため思想もなく書くために書き、仲間同士で誉めあう文章はクズであると言い切る。
「クズどもは待ってましたとばかりに例外的人物の十分に熟考した言説をいじくり回してせっせと自己流に改悪する。」
また、博覧強記の文章をあれやこれやと読んでるうちに、あれもこれもと言える思想の軟弱さがあらわれているとして退ける。そして匿名批評は卑怯者のすることである、と苛烈な批判を加えたあと、
もってまわった言い方が大嫌いなショーペンハウエル
最後に一番厳しい批判を行うのが、言いたいこともないのにもってまわった言い回しで深遠さを出すレトリックの使い手に対してである。
一番長続きするのは「不可解」という仮面だ。これはドイツだけだ。この仮面はフィヒテが導入し、シェリングが磨きをかけ、遂にヘーゲルでその絶頂を迎えた。(p63)
本人が持っている以上の精神性を出すのを物書きは慎む必要がある。また、 素材が重要な鍵となる「何について考えたのか」より「どう考えのか」についての視点が大事である。 ギリシア三大悲劇は同じテーマだが「どう考えたのか」と書き方が違う。それを良く考え抜いたものは素材がシンプルでありながら力強い示唆に満ちている。
ショーペンハウアーの意見を受けて自分なりの拙い反論
こんな感じである。取りこぼした例もたくさんあるが、だいたいはこんなことをショーペンハウエルはこの本の中で述べている。この本が素晴らしいのは一読して、この力強くシンプルに満ちた議論が理解できることである。 というわけで提出用のエッセイでは、これらのことを踏まえ、些細な荒探しにならないように注意し少しずつ反論を試みてみる。
それらの論点は箇条書きで(★が主要な論点とする予定の考え)
★馬鹿な本も面白いことがある→快楽としての読書
・本はすべて真実を突き詰めた思考のきらめきでなければいけないのか?
・ヴァレリーの読書についての意見、それを引用してるバイヤール『読んでない本について堂々と語る本』
★言葉の連なりを戯れのように書く文章、蛇行する文学、もってまわった言い回しの書物は駄目か?
★ここでいう読書は「何かのため」という性質が強すぎないか
・ここでいう本はどのような本なのだろう?と仮に情報だとするならば、もっと射程を広げられないか
・読まないことによって、というがそもそも本は読まれているか
・情報の多様化する中で統一的な思考は可能か?ある程度の数を読まなければわからないこともあるのでは
★コラージュの面白さ、存在しない書物について述べた愛書家ボルヘスなどの事例をどうとらえるか
★書いている途中に自分が思ってもみなかったところへ運ばれることについて
★偉大な思想家が体系を持っていて、多読に適するという基準は何なのだろうか?→おそらく「読書について」で述べられている、「その作家の説得力、イメージの豊かさ・・・は身につかないが、その特性を素質として使う勇気が見つかる」という言及から何らかの意図をもって読み続けるということが必要なのだということ、そして「著述と文体について」で書かれている良い書物の原典にあたり、業界内の有名な引用に満ちた入門書を読むのは避けるという具体的な読書術に結び付く。
いずれにしても、ショーペンハウエル『読書について』は何回読んでも示唆に満ちている。話の議論が具体的だから前回自分が何を思って読んでいたのか把握しやすく、そういう意味で『読書について』は自らの思考を「定点観測」するための本として最適なのである。
ちなみに再読こそ至高とはこの本にも書かれている、むう。 踊らされてる感が(笑)
【関連記事】
関連記事
-

-
「最前線を走る創作者たちとのガチ語り」西尾維新『本題』(講談社)書評
西尾維新:自分の中にはそのつど「今」しかなくて、かっちりと『こうい …
-
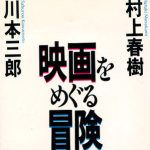
-
村上春樹語る!川本三郎まとめる!貴重な映画本『映画をめぐる冒険』書評
村上春樹の貴重な本といえば若いころに村上龍と対談した『ウォーク・ドント・ラン』が …
-
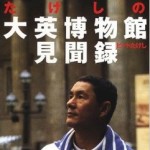
-
【書評】ビートたけしVS大英博物館『たけしの大英博物館見聞録』(新潮社・とんぼの本)
現在、東京都美術館で「大英博物館展―100のモノが語る世界の歴史」が開かれている …
-
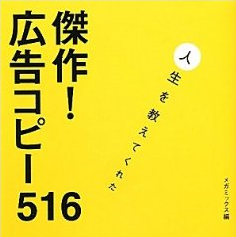
-
傑作の影にクソもあり、メガミックス編『傑作!広告コピー516』(文春文庫)書評
「需要が違うんだから」と女性に言い放つクソ男の台詞とその的外れなダサい広告のせい …
-
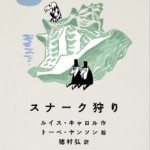
-
【書評】キャロル×ヤンソン×ホムホムの『スナーク狩り』(集英社)はプレゼントに最高の一冊
「不思議の国のアリス」の作者ルイス・キャロル原作! 「ムーミン」の作家トーベ・ヤ …
-

-
嗚呼、ややこしきハラールよ『ハラールマーケット最前線』(佐々木良昭)書評
(内容が厄介なだけに長文です。すまん) Contents1 バンコクで出会った「 …
-
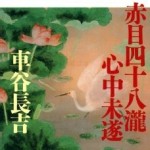
-
【私的印象批評】底を求める/書くことの業『赤目四十八瀧心中未遂』(車谷長吉、文春文庫)
車谷長吉の直木賞受賞作『赤目四十八瀧心中未遂』は、主人公である「私」が数年前に地 …
-

-
上野千鶴子に映画の見方を学ぶ『映画から見える世界―観なくても楽しめる、ちづこ流シネマガイド』感想
数年前に新宿シネマカリテで、レオス・カラックス監督の映画『ホーリーモーターズ』を …
-

-
懐かしいが懐かしいが懐かしい『念力ろまん (現代歌人シリーズ) 』(笹公人・書肆侃侃房)感想
たまたま手に取ってグイと魅了されたこの笹公人の『念力ろまん』は、ただ単純に短歌を …
-
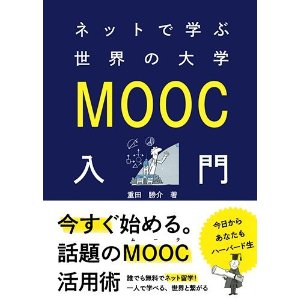
-
~これからは家で留学の時代!?~重田勝介著『ネットで学ぶ世界の大学MOOC入門』(実業之日本社)評
「あなたはMOOC(ムーク)を知っているだろうか?」 …
- PREV
- 2014年8月に見た本と映画
- NEXT
- 『怪談短歌入門』書評~怖さには構造がある、短歌篇~

