デュレンマット『失脚/巫女の死』より「失脚」評
2015/11/26
デュレンマット『失脚/巫女の死』より「失脚」のあらすじ
光文社
売り上げランキング: 193881
力の幻想
個人の意思というものはシステムの中では存在せず、個人はそこではただの記号に過ぎないのではないか、このようなテーマをこれほど鮮やかに描いている小説を久しぶりに読んだ。なにせページを開けて最初に出てくるのがA~Pまで割り振られている図である。アルファベットの「記号」が彼らの名前なのだ。
この小説が凄いのは、通常は登場人物を把握するのに困難となる無個性な記号が、むしろ記号Aを頂点とする権力機構の中でそれぞれの力関係を際立たせる作用として働き彼らの個性を際立たせている点だ。
独裁国家とおぼしき国の「記号」達による最高会議。そこで中心となるのがOの不在である。Oがいったいどうなったのか、誰がその情報を知っているのか、最高権力者であるAは何を考えているのか、出方を誤ると自らも失脚してしまうという極限の状況を読者はNの視点だけをたよりに読み進めていく。
会議に参加していながらある種の観察者として振る舞うNの視点は、しかし、正確な観察者とはなりえていない。N自身はGと対立するDの派閥に属するものと考えているが、「Nは担当部門の専門家以外の何者でもなくDにとってもGにとっても人畜無害な存在だった。NはAにとって吹けば飛ぶような存在だったので、あだ名さえつけてもらえなかった」(p45)と書かれている通り、自身の状況を見誤っている。Nは凡庸で、そして観察も不確かである。しかし、そのように凡庸であることが逆説的に無害な存在という他者の了承を引き出この巨大なシステムの内部にまで上り詰めさせた。
「政治局の十三人の男たちには恐ろしいまでの権力があった。彼らはこの巨大な帝国の運命を決め、無数の人々を追放し、刑務所に入れ、死刑にし、何百万人もの人々の人生に介入し、あっという間に次々と工業地帯を作り、さまざまな家族や民族を強制移住させ、巨大な都市を建設し、途方もない規模の軍隊を編成し、戦争と平和を決定したのである」(p47)
システムは複雑で彼らには絶大な権力がある。
だが物語の途中、偶然にも最高権力者であるAがこの部屋と外部との関係を断ってしまった時からこの場における権力はとても単純なものへと変化した。記号だけとなった世界で明らかにされるのは個人の資質とは関係なく他者との関係性において権力は成立するということだ。
凡庸な意見が武器となり、強固な理論が弱体化したり、圧倒的な空回りが場をかき乱してしまう、そのような事態が密室状態となったこの部屋のなかで繰り広げられていく。十三人の力関係はめまぐるしく変化していく。それは最高権力者であるAとて例外ではない。
個人の特性、外見、思想などは権力を構成するうえで一部分となるが決して本質ではない。Aが最高権力となりえているのは、極端な話Aという記号だからである。アルファベットは単なる文字であるが、漠然と我々はBよりもAが上であるという風にみなしている。そうした暗黙の了解はAがBより先に来るアルファベットの形式上、便宜的に決められているに過ぎない。
つまりAでさえ権力のシステムの中では一つの記号にすぎない。最高権力者というものは存在するが、一時的なものである。それはあるシステムの中で他の記号がその特定の記号を最高の権力とみなしているときにのみ存在する。しかし共同的な主観による相互の取り決めは、ふとしたきっかけで虚飾がはがれる。
「王様は裸である」そして「あんたたちなんかただのトランプじゃない!」というような不意の一言で、そこにあるのは思想や理性でも、ましてや革命のイデオローグでもない、この物語で虚飾を剥がしたのは恐怖心からくる原始的な自己生存本能である。
「権力と互いに関する恐怖心―――それはあまりにも大きかったので、純粋に政治を執り行うことは不可能だったし、理性もそれに打ち勝つことはできなかったのである」(p45)
強いものは弱く、弱いものは強く、めまぐるしく変わる権力の構造転換の果てに何があるか、そこはわれわれにはもう見慣れた光景であるかもしれない、しかしそうした権力の構造と組み換えの瞬間を見せてくれる寓話として、そしてOはいったいどうしたのか?というミステリーとしても「失脚」は素晴らしい物語である。
光文社古典新訳文庫『失脚/巫女の死』はほかにも、いつも乗っている電車が見慣れない状況へと変貌する「トンネル」、あまりにも有名なギリシア悲劇「オイディプス王」を託宣を告げる側からまるで役人の手記のように描く「巫女の死」、車の故障が切っ掛けで村の屋敷に泊まることとなり、ひとつのゲームをすることとなった男を描く「故障」といったデュレンマットの素晴らしい短編が収められている。
共通するのはある種のシステムが狂った時に現実が見せる破れ目、底の底まで堕ちていく感覚である。ひとつの出来事で複雑なシステムが狂い始める寓話がまったく他人事でないと私に思えるのは、現在の社会状況が寓話より寓話らしくなってしまった。そんな感覚を感じるからかもしれない。
【関連記事】
関連記事
-

-
~哲学者の苛烈な批判~、ショーペンハウエル『読書について』(コンクール用の下書き)
毎年、光文社では課題本を設け「古典新訳文庫エッセイコンクール」と称し幅広く文章 …
-

-
闇にさらなる闇を当て、高橋ヨシキ『悪魔が憐れむ歌』(洋泉社)書評
字面から連想されるイメージとは異なり「悪魔主義者」とは絶対的権威を …
-
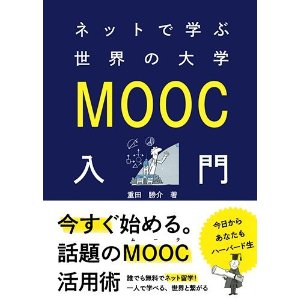
-
~これからは家で留学の時代!?~重田勝介著『ネットで学ぶ世界の大学MOOC入門』(実業之日本社)評
「あなたはMOOC(ムーク)を知っているだろうか?」 …
-
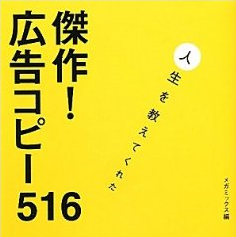
-
傑作の影にクソもあり、メガミックス編『傑作!広告コピー516』(文春文庫)書評
「需要が違うんだから」と女性に言い放つクソ男の台詞とその的外れなダサい広告のせい …
-
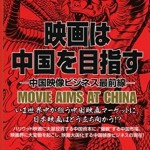
-
【書評】『映画は中国を目指す』(洋泉社・中根研一)
「アイアンマン3」「ダークナイトライジング」「パシフィック・リム」・・・近年のハ …
-
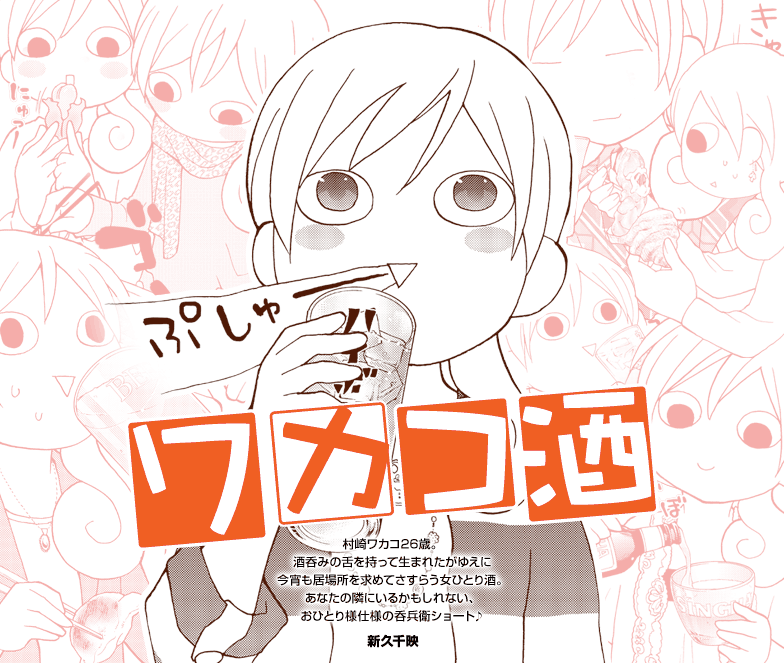
-
本能刺激のはんなりグルメ漫画『ワカコ酒』(新久千映)
最近書店に行くと、食べ物系の漫画がとても増えている。 それらを買って色々と読んで …
-
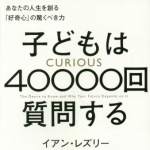
-
子どもが常に好奇心を持っているなんて大間違い!『子どもは40000回質問する』(イアン・レズリー/光文社)感想
40000回、これは2歳から5歳までに子供が説明を求める質問の平均回数だという。 …
-
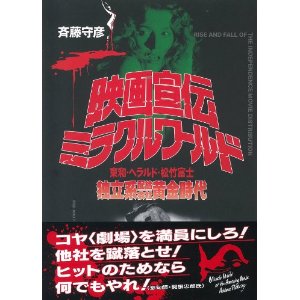
-
【未掲載書評】斉藤守彦著『映画宣伝ミラクルワールド』(洋泉社)~観客に魔術をかけた者たち~
お前のは書評じゃなくてレジュメだと言われて、確かに詰め込みすぎ感はあるということ …
-

-
懐かしいが懐かしいが懐かしい『念力ろまん (現代歌人シリーズ) 』(笹公人・書肆侃侃房)感想
たまたま手に取ってグイと魅了されたこの笹公人の『念力ろまん』は、ただ単純に短歌を …
-
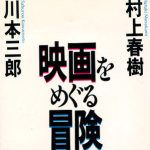
-
村上春樹語る!川本三郎まとめる!貴重な映画本『映画をめぐる冒険』書評
村上春樹の貴重な本といえば若いころに村上龍と対談した『ウォーク・ドント・ラン』が …

