見る人の記憶をこじ開ける写真集『映画館』(中馬聰、リトル・モア)
2015/11/26
あまり映画を見ない家族のもとで育ったので、映画を本格的に見始めた時期は人より遅い。
思春期はと言えば、マトリックスやハリーポッターなどを年に数回家族と見に行くぐらいなもので、語るほどの映画体験は持ち合わせていない。
そんな自分が初めて自らの小遣いで見た映画は「ロード・オブ・ザ・リング王の帰還」だった。地元の小さな映画館で上映しているらしいと友達を誘って行ったのを覚えている。
そして上映が終わり、三部作の完結に感動で涙ぐむ自分たちが外に向かうと、何故か劇場のスタッフが総出で自分たちを見送ってくれた。
この日はその映画館の最終営業日だったのだ。
上映された作品、隣にいた人、自分が考えていたこと、劇場の空気、暗闇から外に出たときの涼しさ、それらすべてを伴って映画館という建物は人の記憶の一部を作り出している。中馬聰写真集『映画館』はそのことを改めて思い出させてくれた。
この写真集は、2007年から写真家の中馬聰が全国の映画館を尋ね歩き、劇場の内部や普段あまり見ることの出来ない作業場やそこで働く人々の様子など「映画館」に関係するものすべてをモノクロで撮影したものだ。
映画「おくりびと」の撮影にも使用された酒田港座(山形県)、銀幕から視界を外せば満点の星が見られる長野県の星空映画祭、車に乗りながら映画を見ることが出来た大磯ドライブインシアター、映画「カーテンコール」の舞台となった前田有楽映画劇場など紹介される映画館は幅広い。
そして、浅草中映劇場、三軒茶屋中央劇場ときたとき思わず涙が出そうになった。
吉祥寺バウスシアター、新宿ミラノ座、新橋文化劇場、シネパトス。
ひとつひとつの建物の写真が、その映画館で見た上映作品と当時の抱えていた悩みとともに蘇ってくる。
映画館が閉館するニュースを聞くたびに、時代が変われば映画館も変わる、時代の流れだ仕方ないと納得したはずだった。なにしろあまり行ったわけではない映画館について自分に何が言えるのだろうか、そんな小さな罪悪感からノスタルジーに浸るのを戒めてきた。
しかし、この写真集はそれを無理やりこじ開けてくる。何かできないだろうかという写真家の思いが、劇場の固そうな椅子やパンを売っている売店など一枚一枚の写真から伝わってきて、街の風景として当たり前に存在していたものがなくなる取り返しのつかなさを訴えかけてくる。
実際掲載されているいくつかの映画館は現在すでに営業を中止している。2007年から2015年はまさにフィルムからデジタルへの移行期であり、耐震補強の予算不足に東日本大震災という未曽有の災害も起きた。だが写された場所が既になくなっている胸の痛くなる事実と同時に、この本はその消えゆく世界を写し取ることに成功したという意味で「間に合った」写真集でもある。
映画館という場所に関して自分に何が出来るのかわからない。ただ映画館を残そうと努力している人々の表情を見て達観することだけはノスタルジーと共に戒めようと考えた。
*「港町キネマ通り」(http://www.cinema-st.com/)は、シネコンから成人館まで全国の映画館を写真入りで紹介しているサイト。凄い。
*また副読本として映画芸術編集部『映画館のつくり方』を読めばこの写真集をより楽しめると思う。
→書評はこちら「映画館はつらいよ『映画館のつくり方』(映画芸術編集部)」
【関連記事】
関連記事
-

-
【書評】『教養は「事典」で磨け』(光文社新書・成毛眞)&おすすめの事典三冊
重く、分厚く、持ち歩くには難しく、値段も高いため余程のことがない限りは開かない「 …
-
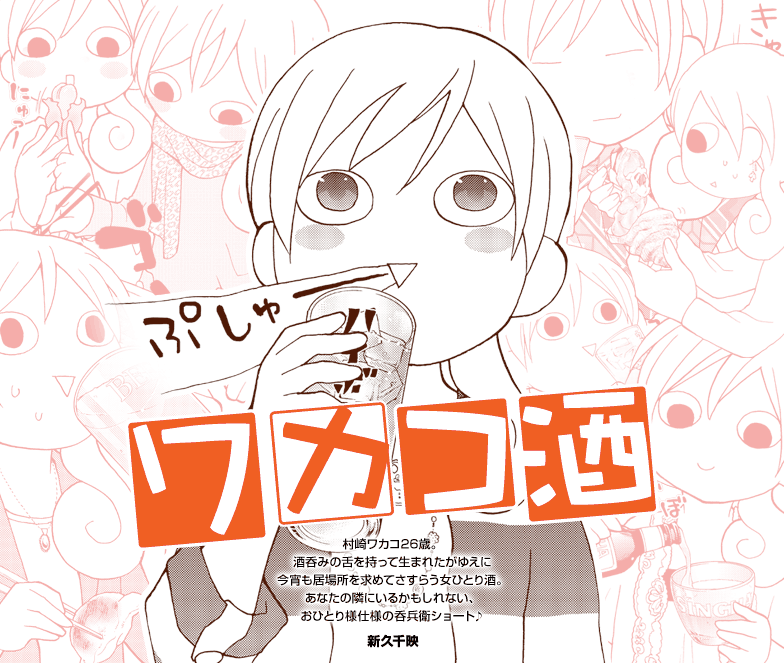
-
本能刺激のはんなりグルメ漫画『ワカコ酒』(新久千映)
最近書店に行くと、食べ物系の漫画がとても増えている。 それらを買って色々と読んで …
-
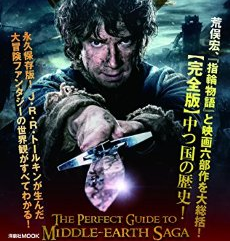
-
いまふたたびの中つ国へ、別冊映画秘宝『中つ国サーガ読本』書評
ビルボ・バギンズ(マーティン・フリーマン)の格好良すぎる表紙に書店で引き寄せられ …
-
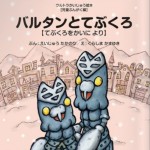
-
名作+怪獣+ウルトラマン=「ウルトラかいじゅう絵本」のカオスな物語たち
ウルトラマン×絵本といえば思い出すのは、子育てに奮闘するウルトラマンやバルタン星 …
-

-
反スペクタクルへの意志『テロルと映画』(四方田犬彦・中公新書)感想
映画は見世物である。激しい音や目の前に広がる大きなスクリーンによって人々の欲望を …
-
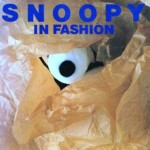
-
スヌーピー95変化!貴重な写真集『スヌーピーインファッション』(リブロポート)
ずっと見たかった『スヌーピーインファッション』をようやく入手。 ええ、たまらなく …
-

-
ホットドッグ大食い大会で日本人はなぜ勝てたのか?危険でおもろい『0ベース思考』(ダイヤモンド社)書評
『0ベース思考 どんな難問もシンプルに解決できる』(スティーヴン・レヴィット/ス …
-
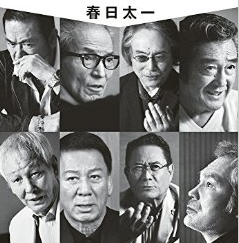
-
生きて語り伝える、春日太一の書籍と最新作『役者は一日にしてならず』(小学館)について
点と点が線になる快感 ドラマも邦画もあまり見てこなかったせいで俳優の名前と顔を一 …
-
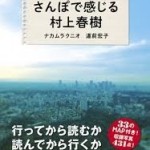
-
ハルキストたちの本気『さんぽで感じる村上春樹』書評
村上春樹についての書籍は多くある。文学的、社会学的な立場からの学術的な書籍も多い …
-
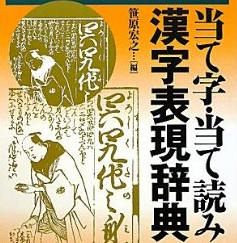
-
運命は「さだめ」な笹原宏之編『当て字・当て読み漢字表現辞典』(三省堂)
今日紹介するのは「妄想型箱舟依存型症候群」と書いて「アーク」と読むサウンド・ホラ …


