ホットドッグ大食い大会で日本人はなぜ勝てたのか?危険でおもろい『0ベース思考』(ダイヤモンド社)書評
2015/11/27
『0ベース思考 どんな難問もシンプルに解決できる』(スティーヴン・レヴィット/スティーヴン・ダブナー著、櫻井祐子訳、2015年2月ダイヤモンド社刊)
『ヤバい経済学』の著者ということでヤバさを察しよう。
本書『0ベース思考』の著者は『ヤバい経済学』において「景気回復が要因ではなく中絶の解禁こそ犯罪の減少に繋がった」等、一般的に信じられている通説とは違った論点を統計的手法を用いてわかりやすく解説し、多くの反響(怒り)を呼んでアメリカに経済学ブームを巻き起こしたスティーヴン・レヴィットとスティーヴン・ダブナーである。
東洋経済新報社
売り上げランキング: 4005
この本は何故二人がそのような社会的慣習や常識抜きで物事を考えることが出来たのかということを、同じような視点を持つ変わり者たちの紹介や分析によって魅力的に説明している。
子育てに熱心な家族の前で「チャイルドシートって時間とお金の無駄だよね」と言ったり、食物の地産地消に熱心な彼女の父親の前で「地産地消ってかえって環境に負荷がかかるんですよ」と言ってしまう二人のエピソードから始まり、イギリスでの深刻な不況を解消するための案を聞かれた際に、かの国の政策の柱でもある「手厚い医療費」を削減すべきと答えた話など冒頭から飛ばしている。
これは食べ放題を選択した消費者は食べすぎてしまうからという話で例えられ、手厚い医療が本当に素晴らしいのかは考える必要があると説明される。ちなみに英の不況について聞いたのは首相になる以前の若きキャメロン、なおかつこの時キャメロンの息子は大田原症候群という病気にかかっていて、まさにこの英国の医療制度によって恩恵を受けていたという事実がある。当然二人はキャメロンからそっぽをむかれる。
ホットドックの大食い大会で日本人が勝てた理由
物事を社会的通念や常識を外して考える「0ベース」という言葉はこれらのエピソードからもわかるように、字面の生真面目さとはかなり異なる。自分が一番やべえと思ったエピソードはアメリカで行われたホットドックの大食い大会で優勝した小林尊の話である。
並み居る太っちょたちを抑えて、体系の細いアジア人がアメリカで優勝できた理由はなんだろうか?しかも一つの事実として彼はただ優勝したわけではなく、前年の倍近い個数である五十二個を食べ、二位を大きく突き放すぶっちぎりの優勝だったということだ。
さて、彼は特別だっただろうかというのが著者の問いかけである。あなたがもしホットドックの大食い大会に参加することになったら、どのようなことをして勝つだろうか?という問いでもある。
答え
彼はどうやってホットドッグをたくさん食べるかではなく、
どうやってホットドックを食べやすくするかを考えたのだ。
まず彼はホットドックの形状を分解していった、つまりホットドッグをそのまま胃に詰めるのではなく、ウインナーを半分に切りパンを水につけ面積を小さくしてシステマティックに胃に詰めていったのだ。そして、彼は大食いをスポーツと定義し直し、そのトレーニング結果を驚くべき勤勉さで細かく計測していった。彼が極端に特別な胃袋を持っているわけではなかった理由として、これ以降ホットドック大会では新記録が続出したという点が挙げられる。彼の「発明」したメソッドによってである。
「0ベース」思考は幼稚さの擁護でもある
他にもこの本が紹介されるとき、良く例に挙げられるのはサッカーにおいてPKのゴールは確率的に真ん中に蹴るのが一番有用というものがある、しかし多くのプレイヤーはそれを選択しない。彼にとってのインセンティブは真ん中にボールを蹴ってもし止められた時、そのことによって起こる自身のイメージ低下を含む、「ただゴールを決めるだけじゃだめなんです」と言うわけだ。
つまりは、はっきり言おう。「0ベース思考」は一般的な格好良さとは異なる。多くの自己啓発書が喧伝しているような、知っていることを大げさに言ったり、どう「上手く」仕事していくかといったことや、知識が洗練されていくことで上手に世を渡り歩けるのだという教えとは異なり、「0ベース思考」は知らないと言うこと、わかるふりをしないことで問題の本質を定義しなおす。
何故多くの人が知らないと言えないか。そう信じられているから、周りがやっているから、なによりもその道につぎ込んできた時間や労力があるから(=サンクコスト)といったことが挙げられる。
それを抜きにして物事を考えてみたらどうなるか、つまりは洗練に対しての稚拙さの擁護という点で「0ベース思考」はバイアスをあまり抱いてなかったときの子供の思考に近い。
終わりに、ひねくれの補強
言いづらいことを言う。人とは違う思いつきを言う。一見それはネットで炎上しがちな、ひねくれた思考で文章を書く人にも出来ているように見える、しかし言えばいいというものではなく、ひねくれたあとに「知らない」という意識があればこそ、しっかりと物事を調べることに手は抜かないということへ当然繋がるだろう。ただの思いつきを「私は凄い」と宣伝するのとは大きく異なる。
自らが拠って立つ習慣や常識を疑い、そこからしっかりと行動へと移った「変わり者」たちの事例と分析は、困難な道にこそ勝機(商機)が広がっていることを教えてくれ、現状に違和感を持つひねくれ者にとって勇気が湧くだろう。ちなみに本書『0ベース思考』の原題は「Think Like a Freak」、直訳気味に訳すなら「「変わり者として考えな!」である。
ダイヤモンド社
売り上げランキング: 475
【関連記事】
関連記事
-
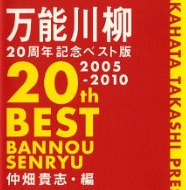
-
264万句のつぶやき、仲畑 貴志『万能川柳20周年記念ベスト版』(毎日新聞社)書評
少し前に広告コピーをまとめた本について書いた時に悪口をたくさん言った。でもその本 …
-

-
デアゴスティーニ『隔週刊 映画クレヨンしんちゃん DVDコレクション』の刊行順にオトナの匂い
最近、書店で見かけてちょっとビックリしたのがデアゴスティーニから刊行された「映画 …
-
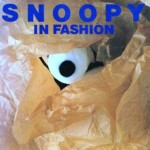
-
スヌーピー95変化!貴重な写真集『スヌーピーインファッション』(リブロポート)
ずっと見たかった『スヌーピーインファッション』をようやく入手。 ええ、たまらなく …
-
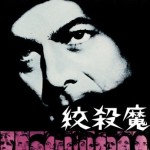
-
血とおっぱいに祝福を『トラウマ日曜洋画劇場』(皿井垂・彩図社)書評
かつてテレビで毎日のように映画を流していた時代があった。 ・・・と、ちょっと前に …
-
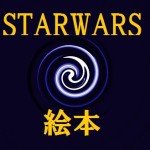
-
スターウォーズ最新作の前にスターウォーズ絵本で優しい気持ちに包まれる
引き続き、12月のスターウォーズ最新作に備えて旧作の見直しと関連書籍を読みふけっ …
-
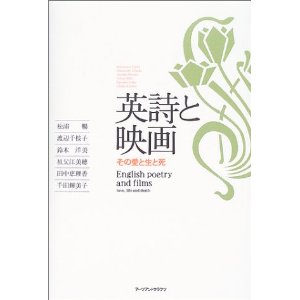
-
映画→詩←映画『英詩と映画』評
検索「映画インターステラー 詩」でこのサイトにたどり着く人が多い。それだけこの映 …
-

-
~哲学者の苛烈な批判~、ショーペンハウエル『読書について』(コンクール用の下書き)
毎年、光文社では課題本を設け「古典新訳文庫エッセイコンクール」と称し幅広く文章 …
-

-
反スペクタクルへの意志『テロルと映画』(四方田犬彦・中公新書)感想
映画は見世物である。激しい音や目の前に広がる大きなスクリーンによって人々の欲望を …
-
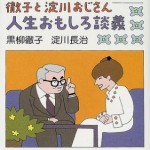
-
【書評】人生の圧倒的な肯定感に満ちた本『徹子と淀川おじさん人生おもしろ談義』
とにかく元気に二人は話す。 「徹子の部屋」に出演した淀川長治と番組パーソナリティ …
-

-
女性器サラリと言えますか?『私の体がワイセツ?!女のそこだけなぜタブー』(ろくでなし子、筑摩書房)感想
検索結果の順位が下がったり、サイト全体の評価が下がったりとそういうことで、グーグ …


![ヤバい経済学 [増補改訂版]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41C-VhgG8CL._SL160_.jpg)
