映画→詩←映画『英詩と映画』評
2015/12/02
検索「映画インターステラー 詩」でこのサイトにたどり着く人が多い。それだけこの映画の中で効果的に詩が使われていたこと、あの詩って何なのだろうという人がいてわざわざ興味を持ってきてくれたということだと思う。
詩というのは、読み手によって多様な解釈がある。その確定できない感じ、意味の分からなさから敬遠する人も多い。けれど、こと映画に引用されているなら、それは多くの場合「台詞」の一部である。台詞の一部である以上、それは監督が何らかの意図をもって引用している可能性が高い。
そしてそれは通常の日常会話よりも何か映画のテーマを決定づけているようなものが凝縮されている。
そういう詩という観点から映画を論じた本としてお勧めしたいのがアーツアンドクラフト社の『英詩と映画』である。
「シェイクスピアのいう’Brevity is a soul of wit’「簡潔が頭の良い証拠」~(中略)~百万言を費やすより何気なく、とみえるが、実は周到に引用された詩の一節や断片が、その映画全体の美学と哲学を構成しているのは興味深い」
この本は詩が出てくる映画21本を取り上げ、日本人にとってはあまり馴染みのない外国詩を作者の経歴込みで見ていくことによってその映画のテーマを掘り下げていく。
こうした「詩を台詞の一部として精査すること」実はこれ、映画コメンテーターもテーマを語るのが嫌いな批評家もあまりやってこなかったためザクザクと面白いものが見つかってくる分野なのである。
例えば、映画『マディソン郡の橋』
このイーストウッド監督・出演の恋愛映画に関しては「ああ、あの不倫映画」、「あんまり面白くない」と言う反応が返ってくることが多い。
しかし実はメリル・ストリープ演じる人妻フランチェスカとイーストウッド演じる旅人ロバートの心がグッと接近する小道具としてイェイツの詩が使われているということをこの本で知った。ロバートがふっと口ずさむイェイツの詩にフランチェスカがサッと返答する。イタリア出身でありながらアイオワの町で日々の生活を送りながらも詩を読み続けるフランチェスカにとって、その交流はどんなに素晴らしいものであったか。
またイエイツの東洋思想がこの作品の終わりのある出来事に影響を与えているのではないかなどの論考も面白かった。いずれにしても「平凡な人妻がちょっと不倫の道へ系映画でしょ」、金曜ロードショーで昔放映した時に「ベッドシーン」があると聞いて正座して待機してたけど「あんまりエロくない!」とこの映画に対して良い印象を持ってなかった自分を戒めてくれる文章だった。
この本は様々な著者が書いているため、その熱の入れよう、文章の巧拙にばらつきはあるが(何を言っているのかわからないヤバい文章もある)知らない映画も多く、知っている映画でも「あれ、そんな場面だったか?」と掲載されている映画が俄然見たくなる。引用の形をとっていない詩の台詞も多く、まだDVDがそこまで普及していない時代に「2年」を費やし書籍にまとめ上げた熱量には本当に頭が下がる。
作者の生きざまから詩を語りすぎているのではないかという指摘もできるが(特に『ザ・フォッグ』で引用されるポーの詩など)
「映画と詩の相互テクストにより多くの人が関心をもち、<修正読み直し>を楽しんで下されば、幸いと望んでます」
と書かれている通り、そうやって詩を読みながら、また映画を見ながら何か別の方向への着想を得たら語り直せばいいのだ。絶えず詩と映画を相互的に読むことによって「映画と詩」と言うテーマはさらに豊饒なものとなるだろう。
この本には平凡社ライブラリーから出ている続編的なものもあり、(収録映画、テクストは一部重複)これに興味を持った人は読んでみるといいかもしれない(コンパクトだし)
そしてさらに詩が出てくる映画、そもそも根源的に詩と映画と言うのはどういう関係性を持っているのか探究したい人には、『Edge』という本がオススメだ。現代詩人たちが映画について語るシンポジウムを多数収録していて、刺激的だし何よりも巻末に付されている東西問わず「詩に関係する映画」一覧表は圧巻!
(『英詩と映画』に出てくる映画と詩の収録作は以下の通り)赤字は自分が好きだった論考。
- 「哀愁(マーヴィン・ルロイ監督、1949年)」(H.W.ロングフェロー「失われし青春」)
- 「ソフィーの選択(アラン・J・バクラ監督、1989年)」(E.ディッキンソン「このしとねをひろくしてね」)
- 「草原の輝き(エリア・カザン監督、1961年)」(ウィリアム・ワーズワース「永世に親しむうた」)
- 「逢びき(デヴィット・リーン監督、1965年)}(ジョン・キーツ「死の恐怖」)
- 「恐怖のメロディ(クリント・イーストウッド監督、1971年)」(エドガー・アラン・ポー「アナベル・リー」)
- 「剃刀の刃(エドマンド・グールディング監督、1946年)」(ジョン・キーツ「あの日は、去った」)
- 「アウトサイダー(フランシス・コッポラ監督、1983年)」(ロバート・フロスト「黄金色はいつまでも続かない」)
- 「ハンナとその姉妹(ウディ・アレン監督、1986年)」(e.e.カミングズ「私が旅したことのない何処か」)
- 「愛しすぎて 詩人の妻(ブライアン・ギルバート監督、1995年)」(T.S.エリオット「リトル・ギディング」)
- 「デンジャラス・マインド卒業の日まで(ジョン・スミス監督、1991年)」(トマス、ディラン「あの快い夜の中へおとなしく流されてはいけない」、ボブ・ディラン)
- 「ザ・フォッグ(ジョン・カーペンター監督、1979年)」(エドガー・アラン・ポー「夢のまた夢」)
- 「愛と哀しみの果て(シドニー・ポラック監督、1985年)」(サミュエル.T.コールリッジ「老水夫の歌」)
- 「チャタレイ夫人の恋人(ケン・ラッセル監督、1995年)」(ロバート・ヘリック「乙女たちへ、時を惜しめと」)
- 「オルランド(サリー・ポッター監督、1992年)」(エドマンド・スペンサー『妖精の女王』第二章)
- 「エンジェル・アット・マイ・テーブル(ジェーン・キャンピオン監督、1990年)」(ロバート・バーンズ「ダンカン・グレイ」)
- 「ワイルド(ブライアン・ギルバート監督、1997年)」(オスカーワイルド『レディング監獄のバラッド』より)
- 「ピアノ・レッスン(ジェーン・キャンピオン監督、1993年)」(トマス・フッド「沈黙」」)
- 「ジェイン・エア(バリー・レッツ監督、1996年)」(ウォーター・スコット『マーミオン』)
- 「マディソン郡の橋(クリント・イーストウッド監督、1995年)」(W.B.イェイツ『さまよえるインガスの歌』)、
- 「愛の7日間(ディック・リチャーズ監督、1983年)」(シェークスピア「ハムレット」第一幕、j.p.c.フロリアン「愛のよろこび」)
- 「サマー ストーリー(ピアス・ハガード監督、1988年)」(ジョン・キーツ「冷たい美女)
【関連記事】
関連記事
-
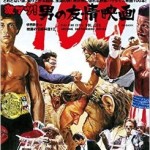
-
【書評】読んで燃えろ、見て燃えろ『激アツ!男の友情映画100』(洋泉社・映画秘宝EX)
【友人として、相手を思い、また裏切らぬ真心】とは「新明解国語事典第6版」に記載さ …
-

-
【書評】家庭科を食らえ!『シアワセなお金の使い方 新しい家庭科勉強法2』(南野忠晴、岩波ジュニア新書)
「ああ学生時代もっと勉強しとけば良かった」 こんな言葉に巷で良く出会う。「どの教 …
-
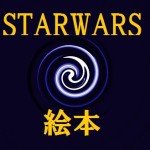
-
スターウォーズ最新作の前にスターウォーズ絵本で優しい気持ちに包まれる
引き続き、12月のスターウォーズ最新作に備えて旧作の見直しと関連書籍を読みふけっ …
-

-
女性器サラリと言えますか?『私の体がワイセツ?!女のそこだけなぜタブー』(ろくでなし子、筑摩書房)感想
検索結果の順位が下がったり、サイト全体の評価が下がったりとそういうことで、グーグ …
-
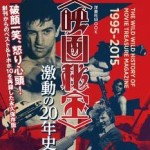
-
This is eigahiho!『<映画秘宝>激動の20年史』 (洋泉社MOOK)感想
タイトルは『300』的なノリで。 現在も大々的に刊行されている映画雑誌といえば『 …
-
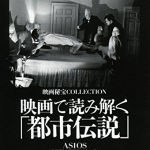
-
貞子は実在した!?『映画で読み解く都市伝説』(ASIOS・洋泉社刊)
呪い、陰謀、超能力、アポロ計画、UFO、超古代文明……。 これらの題材は映画とい …
-
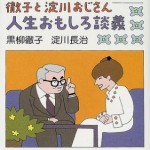
-
【書評】人生の圧倒的な肯定感に満ちた本『徹子と淀川おじさん人生おもしろ談義』
とにかく元気に二人は話す。 「徹子の部屋」に出演した淀川長治と番組パーソナリティ …
-
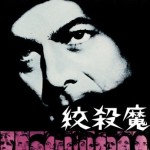
-
血とおっぱいに祝福を『トラウマ日曜洋画劇場』(皿井垂・彩図社)書評
かつてテレビで毎日のように映画を流していた時代があった。 ・・・と、ちょっと前に …
-
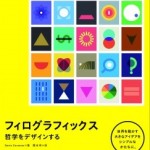
-
【書評】言葉以外を武器として『フィログラフィックス 哲学をデザインする』(ジェニス・カレーラス・フィルムアート社)
フィルムアート社から4月に出版されたジェニス・カレーラス著『フィログラフィックス …
-
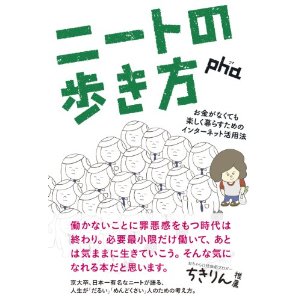
-
pha著『ニートの歩き方』(技術評論社)評~走らない生き方~
前回の記事『無業社会』の書評で働いてないことへの抑圧を軽減することも重要である。 …


![マディソン郡の橋 特別版 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51YON4zKO7L._SL160_.jpg)
