貞子は実在した!?『映画で読み解く都市伝説』(ASIOS・洋泉社刊)
呪い、陰謀、超能力、アポロ計画、UFO、超古代文明……。
これらの題材は映画というメディアに、ときには馬鹿げたB級作品として、ときには真面目な「実話」系作品として繰り返し引用される。
洋泉社から刊行された『映画で学ぶ都市伝説』は、「Association for Skeptical Investigation of Supernatural」(超常現象の懐疑的調査のための会)=通称「ASIOS(アシオス)」が、それら映画に流入した都市伝説がいったい本当はどのような事件だったのかをX-FILEの捜査員以上の実力で徹底追求した本である。
洋泉社
売り上げランキング: 8104
実際にあったと言われる悪魔祓い事件をもとにした『エクソシスト』、兵士を薬物によってコントロールしようとしたCIAの実験「MKウルトラ」を題材にした『エージェント・ウルトラ』、他にも「アポロ陰謀論」を下敷きにした『カプリコン・1』など本書で取り上げる都市伝説は多種多様。
題材が多岐に渡るため本書に興味を持つような人は当然知っている話題も多いだろう。
しかし映画を切り口にして都市伝説を深く探っていく映画本は今まであまり存在しなかった。アシオスは英語文献の解読や実地調査をすることで神秘のベールをボロボロと剥がしていく、そのことに都市伝説好きとしてまったく嫌な思いをしないのが本書の凄いところである。
なぜなら本書はTVタックルの大槻教授のように相手を論破しようというのではなく、好奇心で物事の謎を解明しようとする精神で突き進んでいくからだ。
ポニーキャニオン
売り上げランキング: 19032
たとえば『リング』に出てくる呪いのビデオ、その呪いの起源として劇中で念写の事件が語られるのだが、それは1910年に日本で実際に行われた公開実験が元となっている。
映画では念写に成功したものの世間や学者からインチキだと叩かれたために女性は絶望し自殺するという結末だったが、現実においてはこの実験が行われたことがきっかけで「千里眼ブーム」が起きたというのが面白い。
この論考を執筆した著者の調査によると「貞子」のモデルはこの実験に参加した女性とその後実験の提唱者である博士が出会った高橋貞子という人物が元となっているとのこと。しかしその高橋貞子さんも特に絶望堕ちすることなく晩年は郷里の岡山で心霊治療をして特に恨んで死んだわけではないようだ。との報告にホッコリ。
Happinet(SB)(D)
売り上げランキング: 68205
また「M資金」の話題も面白かった。M資金は本土決戦に備えて隠匿していた財産がGHQに押収されずいまも極秘裏に運用されているといったたぐいの都市伝説である。正直これは自分は相当信じていた。なんかまあ、あるんじゃないかなぐらいの気持ちで。
でもどうやら「一部の人しか知らないお金を運用している謎の人物」という語り方は詐欺話の常套手段として古くから存在するというのだ。(「スペインの囚人」という手口らしい)
都市伝説は本当に面白い。ある平凡な事件が、別の事件との間に類似性を発見した瞬間その出来事は輝きを増し背後関係や意味を求め始める、いわば出来事を偶然ではなく必然だと思ってしまう。結果としてある映画に出演した俳優や携わったスタッフがたまたま何人か亡くなったことでその作品を呪われた映画と名指したり、上空に怪音が鳴り響いた現象が続くと「黙示録のラッパ」だと信じる態度が生まれる。
面白さで済んでいるうちはまだよいが、力あるフィクションがときにはある種の偏見や悪意ある陰謀論と結びつくと非常に恐ろしいことにもなる。だから「はい!いったん目を覚ましましょうね!」と優しく面白く語ってくれる本書はとても貴重で重要な著作だと思う。
関連記事
-

-
山同敦子『めざせ!日本酒の達人』書評~基礎ほど熱いものはない~
Contents1 飲んだ酒を思い出せない!2 予測を立てるための知識3 「辛口 …
-

-
嗚呼、ややこしきハラールよ『ハラールマーケット最前線』(佐々木良昭)書評
(内容が厄介なだけに長文です。すまん) Contents1 バンコクで出会った「 …
-

-
人類を存続させる思いやり『中原昌也の人生相談 悩んでるうちが花なのよ党宣言』(中原昌也、リトル・モア)感想
「中原昌也」の「人生相談」、タイトルの段階でこの本は面白いに決まっているが、最初 …
-

-
反スペクタクルへの意志『テロルと映画』(四方田犬彦・中公新書)感想
映画は見世物である。激しい音や目の前に広がる大きなスクリーンによって人々の欲望を …
-

-
デアゴスティーニ『隔週刊 映画クレヨンしんちゃん DVDコレクション』の刊行順にオトナの匂い
最近、書店で見かけてちょっとビックリしたのがデアゴスティーニから刊行された「映画 …
-

-
新作STARWARSに備えるためには河原一久のスター・ウォーズ本が良いぞ
2015年はスター・ウォーズの新作が公開されるということもあって世界中で盛り上が …
-
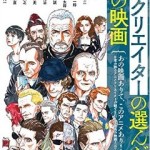
-
【書評】映画秘宝とオトナアニメの究極タッグがついに聞き出した!『アニメクリエイタ―の選んだ至高の映画』(洋泉社)
アニメクリエイターが映画について語る語る 複数のアニメクリエイターが映画について …
-
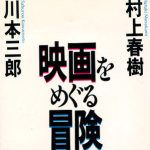
-
村上春樹語る!川本三郎まとめる!貴重な映画本『映画をめぐる冒険』書評
村上春樹の貴重な本といえば若いころに村上龍と対談した『ウォーク・ドント・ラン』が …
-

-
寝る前にアントニオ・タブッキ『夢の中の夢』(岩波文庫)を読む
読書日記をつけてみることにしました。まずは一冊目として タブッキ『夢の中の夢』に …
-

-
闇にさらなる闇を当て、高橋ヨシキ『悪魔が憐れむ歌』(洋泉社)書評
字面から連想されるイメージとは異なり「悪魔主義者」とは絶対的権威を …


![リング コンプリートBOX [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/21SGJRCC44L._SL160_.jpg)
![人類資金 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51%2BSqwLkHGL._SL160_.jpg)