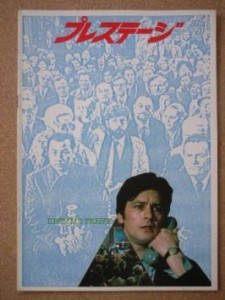書評『田中小実昌エッセイ・コレクション3「映画」』食べて、見終えて、酒飲んで
2015/11/26
平日、引っ越しを手伝いに遠出をして郊外のイオンに行った。
その店舗二階にあるゲームセンターの情景が素晴らしかった。
大学生グループが子供用のコインゲームを寝ころびながらプレイしている横で、明らかに中学生と思われる男子の遊ぶ太鼓の達人をクレーンゲームに寄り添いながら見ている綺麗な店員のお姉さん。この流れ、すべてが完璧な秋の怠惰な一場面。
そこで田中小実昌の『エッセイコレクション3映画』を読んだものだから、それはもう極上の読書体験であった。
木曜日、いなり寿司(五コ六十三円)を買って蒲田駅西口のパレス座に行く。どんな計算で六十三円になり、いったい、一コいくらなのか、だいぶ考えたがわからない。
キップ売り場には、オトナ割引百五十円と書いてあった。「いま割り引き時間?」とテケツの女の子にきいたら「いいえ」という返事。とにかく百円玉を二つ出すと十円玉が五つかえってきた。こいつも、よくわからない。なかにはいると、マラソン優勝者のアベベに似た、色が黒い、どこの国の人間だか見当がつかない男が、宍戸錠をぶんなぐったところだった。
「息子を信じる前にごらんなさい」より抜粋
本書は作家である田中小実昌が1964年から途中10年の間をおいて1990年まで様々な書籍で発表した映画についての文章を再構成したものである。
冒頭の引用文からもわかるとおり実にゆるい。
そして、ゆるくありつつも映画館の周辺情報を含め観た映画について、つらつらと書きつらねていく文章にたまらない魅力がある。
何を上映しているか調べずに映画館に入り、途中から見始め、終わった後でタイトルを確認するような書き方で、キチンとしまらない映画を愛する性格が文章に如実に現れている。けれどマメである。映画が終わったら酒を飲み、ふらふらと潰れ、翌朝には仕事をして、ふらふらなるままに試写会ではなく遠くの映画館まで散歩する。一人の映画好きとしてずーっとそれを続けていたことがこの本を読むとわかる。
弁当を食べたり、途中から見ても大丈夫な三本立ては当たり前、街を歩けば映画館を見つけられる。現在の見逃した映画はDVDで、古い映画を見ようとすることは下手をすれば最新の映画を見るより大変という慌ただしさを考えると、ここに書かれていることはフィクションのよう。
「ぼくが、場末の映画館で三本立てを見るのは、入場料が安くて、電車賃がかからないためばかりではない。三本立てだと、たいていおもしろくない映画がひとつやふたつはある。それを我慢してみることで、人間は深みを増す」
(本書抜粋)
というわけで、こういう余裕のある鑑賞態度をとることは今では難しい。しかしこの本の無類の面白さを考えると、余計にこの言葉の重大さが解る。
つまり、だらだらしているからこそなのだ。
だらだらしているからこそ不意に素晴らしい映画に遭遇する状況が生まれ、途中から見ても良い映画だと思ったら最後まで真剣に見るという集中力が発揮できる。そういう態度でスヌーピーやゴジラに寅さん、外国のハードボイルドにカサヴェテスまで見ていく「コミさん」の鑑賞スタイルから出る発言は時に鋭い。途中からでも筋のわかってしまう映画にため息をついたあと、日活ロマンポルノはポルノを見せ場とするため筋を排除したところに素晴らしさはあるといった発言などがその典型だ。
また『プレステージ』に出てくる、やたら忙しそうな演技をする美術商役のアラン・ドロンを見て
「アラン・ドロンがいそがしい男になった。わるい風潮だな。いそがしいというのは異常なことで、けっしていいことではない。ふつうでいいじゃないの、ふつうで・・・。」
収録されている「ぼくのB級映画館地図」などは、街中で映画を適当に見ることが出来た時代の素晴らしい証言ともなっている、「知性美なんてものはない」と言い切る女優論という名の暴言も昭和文士といった感じで、こんなに数多くの作品が様々な街で見られたことに羨望と遠い思いを抱く。
しかし繋がりはまだある。早稲田駅で降りて昔の「早稲田松竹」へ向かう「コミさん」は高田馬場から降りたほうが早かったとぼやき、ベルトルッチ『暗殺の森』を見て不思議な映画館で不思議な映画を見たと述べる。また原町田駅の近くで女の子と泥酔するほど飲んだ後に「ついでだが、原町田で、昔からあったけとばし(馬肉)屋をさがしたが、わからなかった」と柿島屋を探すあたりの風景描写は地元民としてクスリとしてしまう(わかりづらい場所なのだ)
確かに街から映画館は少なくなった。昭和文士の時代も遠くなった。
けれど、個人としては心意気だけでもそうしたファンタジィを導入すべきではなかろうかと、それもある種の豊かさではないかと、ここイオンの怠惰な空気に触れて思うのだ。現に店長に叱られても気にしない店員のお姉さんの飄々とした態度を見ていると、ますますそう確信してくる。
このような内容を後日、人に話したら白い眼で見られて大変つらい感情を抱き、だらだら書くつもりだったこの文章も思いのほか時間がかかった。
ダラダラでありながら面白くあるのはとてつもなく難しいと「一億総活躍社会を目指す」といった演説がテレビを流れた夜に思う。
【関連記事】
- 映画の本となると話はどこからでもはじまる講演会「映画批評をめぐる冒険」第三回まとめ(講師:佐野亨、モルモット吉田、岡田秀則)
- 映画+散歩+珈琲=『東京映画館 映画とコーヒーのある一日』(キネマ旬報社)感想
- 生きて語り伝える、春日太一の書籍と最新作『役者は一日にしてならず』(小学館)について
関連記事
-

-
山同敦子『めざせ!日本酒の達人』書評~基礎ほど熱いものはない~
Contents1 飲んだ酒を思い出せない!2 予測を立てるための知識3 「辛口 …
-

-
『怪談短歌入門』書評~怖さには構造がある、短歌篇~
Contents0.0.1 1 陰翳礼讃、隠すことの美学2 定型詩には、隠すこ …
-

-
女性器サラリと言えますか?『私の体がワイセツ?!女のそこだけなぜタブー』(ろくでなし子、筑摩書房)感想
検索結果の順位が下がったり、サイト全体の評価が下がったりとそういうことで、グーグ …
-

-
不穏と平穏とそのあいだ、いがらしみきお『今日を歩く』(IKKICOMIX)
『ぼのぼの』の原作者いがらしみきおが休刊となった月刊IKKIのWEBコミックサイ …
-
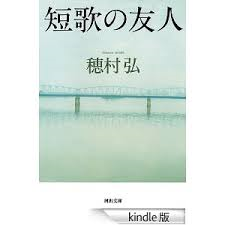
-
穂村弘『短歌の友人』書評~友達作りの方法論~
「俺にもできる」 短歌を作ろうと思ったのは1年ぐらい前に読売新聞を読んでいた時だ …
-
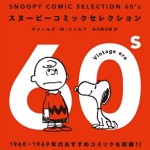
-
初めてスヌーピーの漫画を読むなら『スヌーピーコミックセレクション』(角川文庫)がおすすめ
今年は漫画、本・カフェ・アニメ・グッズなどありとあらゆるところでスヌーピーが流行 …
-
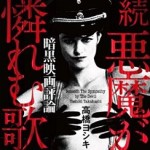
-
【書評】闇があなたを見ている『続悪魔が憐れむ歌』(高橋ヨシキ著、洋泉社刊)
光と闇に分けられない曖昧な部分が描かれた映画、そこに目を向けるという点でこの続編 …
-
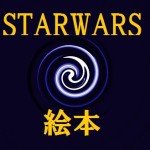
-
スターウォーズ最新作の前にスターウォーズ絵本で優しい気持ちに包まれる
引き続き、12月のスターウォーズ最新作に備えて旧作の見直しと関連書籍を読みふけっ …
-

-
人は死ぬとき何を詠うか『辞世の歌』(松村雄二・三笠書房コレクション日本歌人選)
体調を崩してからヴァージニア・ウルフやボラーニョ、伊藤計劃の日記などを意識して読 …
-
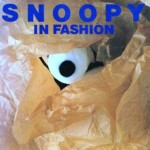
-
スヌーピー95変化!貴重な写真集『スヌーピーインファッション』(リブロポート)
ずっと見たかった『スヌーピーインファッション』をようやく入手。 ええ、たまらなく …