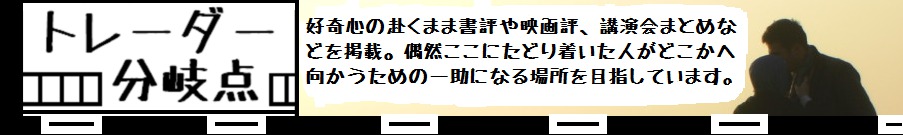仄暗い水の底で遊戯を『夜のゲーム』(オ・ジョンヒ/段々社)感想
「閉塞感」というのは、「ここではないどこかへ」という意識ではなく「ここから逃げたいが、しかしどこにいっても結局は変わらない」という諦観を言うのかもしれない。
そんなことをオ・ジョンヒ『夜のゲーム』を読んで考えた。
オ・ジョンヒ『夜のゲーム』あらすじ
「何もかもが昨日と変わらない」と「夜のゲーム」の主人公である「私」は言う。
汚れた台所を掃除し、夕飯の準備をして、そこから丘の上にある少年院へ帰る作業終わりの少年たちを見つめる。
三人分の箸を準備したところで、一人分の箸を戻す。どうやら主人公の兄はしばらく前に家を出たらしい。
「<いかさまだ>ある日、兄さんがとつぜんテーブルをゆすって立ち上がり、張りつめていた紐のはしを放してしまったとき、三角の構図は崩れて、その反動で父と私はひどくよろめいた」
(本書p32より)
時刻は夕方から夜へ。テーブルには年老いた父と娘が向かい合って食事をしている、兄がいた頃にはお互いに向かい合う必要はなかった。父の顔に老いを見て、そこに自分の老いを投影することもなかった。
陰鬱な夕食が終わり、そして周囲が真っ暗になると、世界から切り離されるような、ぼんやりとした明かりがともる部屋の中で二人の「花札」遊びが始まる。

感想:仄暗い不快な底に囚われる文体
短編であるが、ある種の不快な感触は、読者に息苦しさを感じさせる密度の濃い物語となっている。
たとえば、それは漢方薬の「刺激臭と煙と汚れ」だったり、父の「びしょびしょの手」だったり暗くじめじめとした表現に顕著である。
そうした不快な状況に拍車をかける装置が夜に父娘が遊ぶ「花札」である。
ここで行われるゲームは娯楽のためのものでも退屈しのぎに遊ぶものでもない。ヨレヨレの花札は傷のため、相手が何を持っているか分かっている。わかった上で二人は「演技」をしている。
「裏返しに持っているより絵の面を相手に見せたほうがトリックの余地があると言えるくらい、父と私は花札の裏面に精通しているのだ」
(本書p22より)
「父と私は、古くてよれよれになった台本で、ひっきりなしに劇を演じていた」
(本書p27より)
しかしこうした茶番に侵入してくるものがある。
それは外から聞こえてきた口笛の音や、引っ越してきた女性が我が子に歌う二階から聞こえる子守歌だ。
侵入してくるノイズによって「わたし」は過去の記憶を断片的に呼び起こす。兄が出て行ったこと、母がまだ小さかった赤ん坊を殺してしまったこと、そのために父が祈祷院に母を入れたこと、そして花の香りである。
淀むような湿っぽい匂いの中で繰り返される「花の香り」という表現は一見プラスのイメージと繋がっているように思えるが、それは亡くなった母に関係のある「死」の匂いなのだ。
「死臭をただよわせはじめた母さんからは、やはり煙みたいにつんとする花の香りがした」
(本書p42より)
汚濁を隠す香水の匂いは主人公が家の外で人に抱かれているときにも感じ、眩暈をおこす。
そうした死の匂いから遠ざかろうと「私」はこの家から逃げ出すことを考えている。
「私も兄さんみたいに、ぷいっと出ていくことができるだろうか。沈没する船体から救命胴衣を着て必死に脱出するように、ああやって逃げ出すことが出来るだろうか」
(本書p33より)
だが「私」はこうした思いと同時に「だけど、どこだって同じなのよ」(p33)という諦念も感じている。
この両者の立場で葛藤し、動けないでいる状況こそ、この小説の「閉塞感」である。
「どこだって同じ」だからこそ、このままこの家で待ち続ける受動的な行為はいずれ来る「死者」の世界にこの家が飲みこまれることを意味する。
「私」の体調の悪さや眩暈、切れかかった電灯や不鮮明なテレビがそれを暗示している。
だが重要なのはそこから逃げ出す主体性への萌芽も描かれている。それは茶番が描かれている台本=花札はすでにボロボロだということだ。
「やはり花札の新しいのを一組買わなくては。相手の花札がわかってるゲームなんて面白くない」
(本書p36より)
また、詰まっていた排水管が修理工によって修復されたため、台所から腐臭が消え去ったこともこの物語の中での数少ない汚れが綺麗になる「聖」の感覚である。
汚濁が消え去る2つの出来事はこの物語において数少ない。始まるゲームは新しいものとなり。排水溝がもう詰まることはないだろう。時間が経ち、それが再び元に戻るまで。
変わらないから待ち続ける受動性と、ここから飛び出ようとする主体性の葛藤はラストシーンにおいて示唆的である。
「やがて家全体が軋みながら泥沼のような闇の中へとじょじょに潜水しはじめた。頭上の女は沈没する船のマストに結ばれた救助信号の古い布切れのように、一晩中、ひたすら空しく翻っていることだろう」
(本書p43より)
死者の空気が家を覆っていても、二階の母はひたすらあやし続け、子供は生きる限り泣き続ける、それはいくら空しくても紛れもなく救助信号なのだ。
最後に主人公は笑う。それが諦めなのか生の肯定なのかは読者に委ねられている。
私はこう思う。最後の笑いは「閉塞感」という、ここを抜け出して、どこに行っても変わらないという諦めを知りつつも、それでも生きていくことへの主体性をみせる世界へのせめてもの意思表示なのだと。
関連記事
-

-
映画『リトルプリンス星の王子さまと私』を見る前に再読しませんか原作
2015年11月21日に公開される映画『リトルプリンス星の王子さまと私』は、とあ …